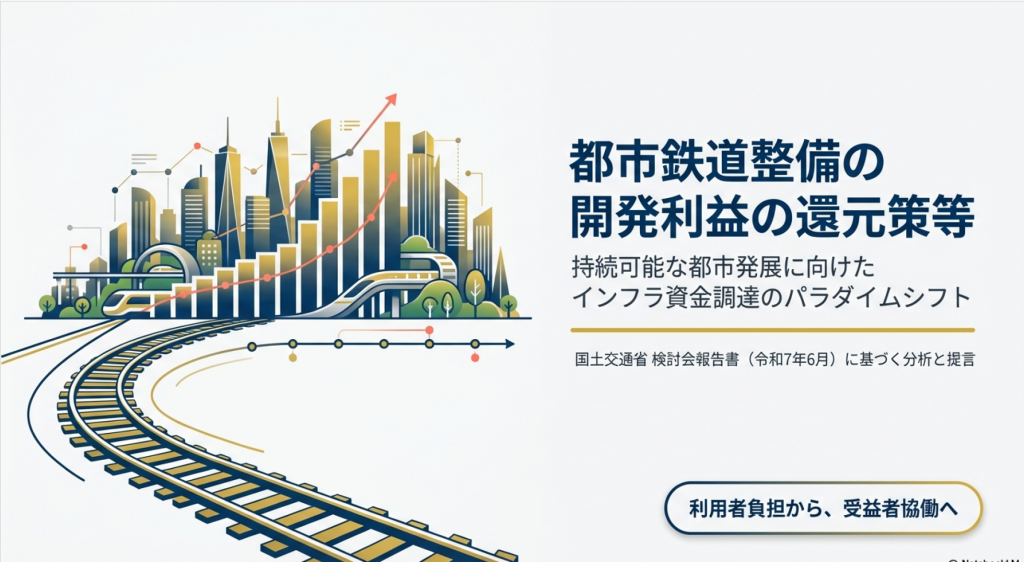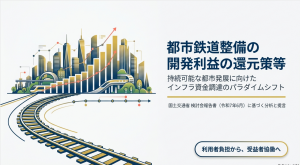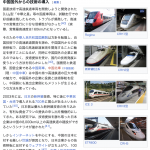都市鉄道は、日本の都市が持続的に発展していくための基盤となる交通インフラです。環境負荷が低い交通手段であることから、2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること)や脱炭素社会の実現に寄与する存在としても重要視されています。しかし、今、この都市鉄道の維持と整備がかつてない困難に直面しています。シリーズ第1回では、鉄道経営が直面する現状を整理し、なぜ利用者以外の受益者(利益を受ける人)にも負担を求める必要があるのか、歴史的な視点を交えて考えていきます。
目次
本論の元となった資料
出典: 今後の都市鉄道整備の促進策のあり方に関する検討会報告書
日本の持続可能な都市発展とカーボンニュートラルの実現に向けた都市鉄道整備の促進策について、その費用負担のあり方を論じた検討会の報告書です。鉄道整備は利用者の利便性向上のみならず、沿線地域の地価上昇や自治体の税収増といった広範な開発利益をもたらしますが、人口減少やコロナ禍による鉄道事業者の経営悪化により、従来の手法では大規模投資が困難になっています。そのため、不動産所有者や開発者、行政など、鉄道の存在によって間接的に恩恵を受ける幅広い受益者による費用負担の重要性を提言しています。具体的には、つくばエクスプレスやみなとみらい線といった国内の還元事例や海外の公的制度を分析し、定量的なデータに基づいた合意形成のポイントを整理することで、次世代の都市インフラ整備に向けた柔軟な仕組みづくりを後押しすることを目的としています。
第1回:なぜ今「受益者負担」なのか?——鉄道経営の危機と「黄金時代」の教訓
都市鉄道を支える基盤の揺らぎ
日本の三大都市圏において、公共交通機関を利用する人の約9割が鉄道を選択しています。大量の人数を高速かつ安全に、そして正確な時間で運ぶ能力を持つ都市鉄道は、日々の通勤や通学だけでなく、あらゆる社会経済活動を支える生命線です。東京圏の整備延長(線路の長さ)を見ると、昭和31年には約1500キロメートルであったものが、令和3年には約2461キロメートルまで拡大しました。これまでは、増加し続ける人口と郊外への居住地拡大に対応するため、輸送力(運ぶ能力)を増強するという量的な拡大が中心でした。
しかし、現在、鉄道を取り巻く環境は大きく変化しています。日本の総人口は減少局面にあり、三大都市圏の夜間人口(その地域に住んでいる人口)も、首都圏では令和2年、近畿圏や中部圏では平成22年をピークに減少に転じています。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響による行動様式の変容(生活習慣や働き方の変化)が決定的となりました。在宅勤務やオンライン会議の普及により、鉄道の利用者はコロナ禍前の水準には戻っていません。今後、中長期的に人口が減っていくことを踏まえると、輸送需要が再び大幅に拡大することは見込めない状況です。
深刻化する設備投資の停滞
利用者の減少は、鉄道事業者の経営に直結しています。JR本州3社や大手民鉄16社は、コロナ禍において営業利益が赤字となりました。令和5年度には黒字を確保したものの、営業収益は依然としてコロナ禍前の水準に達していません。この経営状況の悪化は、将来に向けた投資に影を落としています。
大手民鉄16社の設備投資額を見ると、令和元年度の合計は約4920億円でしたが、令和5年度には約3748億円まで減少しました。特に深刻なのは、安全に関わる投資は一定水準を維持している一方で、サービス改善や輸送力増強のための投資が大幅に削減されている点です。令和元年度に約2234億円あったこれらの投資は、令和5年度には約1077億円と、半分以下にまで落ち込みました。このように、鉄道事業者が単独で大規模な設備投資を伴う都市鉄道の整備に積極的に取り組むことは、現在、きわめて慎重な判断を要する事態となっています。
かつてのエコシステムと三位一体モデル
鉄道の整備費用をどのように調達するかという問題は、今に始まったことではありません。歴史を振り返ると、かつての鉄道経営には、鉄道単体の運賃収入に頼らない持続可能なビジネスモデルが存在していました。それは、鉄道と電力、そして不動産開発を一つの企業グループが担う垂直統合型(関連する複数の事業を一体的に経営する形態)の仕組みです。
19世紀末から20世紀初頭にかけて、特に私鉄経営においてこのモデルが確立されました。鉄道会社が延伸先の土地を安く購入して住宅地として開発し、鉄道を敷設することで土地の価値を高め、その売却益や沿線での商業活動から得られる利益を鉄道の建設資金に充てるという好循環が生まれていました。さらに、安定した収益を生む電力事業を兼業することで、鉄道部門の赤字を補填する内部補助(社内の他部門の利益で補うこと)も行われていました。
しかし、この強力なスキーム(仕組み)は、法制度の変化によって解体されることになります。米国では1935年の公益事業持株会社法により、電力と鉄道の兼業が厳しく制限されました。日本でも戦後の独占禁止法や過度経済力集中排除法などの影響により、鉄道と電力の分離が進みました。これ以降、鉄道事業者は主に運賃収入を原資(もととなる資金)として、多額の建設費や維持費を賄わなければならない構造へと変化していったのです。
受益者負担という新たな視点
現在の厳しい経営環境下で、以前と同じように鉄道事業者と利用者だけの負担で新線建設や駅の改良を進めることには限界があります。そこで重要となるのが、鉄道整備によって利益を得ている幅広い主体に目を向ける受益者負担の考え方です。
鉄道事業は、直接の受益者である利用者に運賃負担を求めることが基本です。しかし、鉄道が整備されることによる効果は、利用者以外にも幅広く及んでいます。例えば、鉄道の新設や駅の設置によってアクセシビリティ(目的地への到達のしやすさ)が向上すると、時間短縮や混雑緩和といった消費者余剰(利用者が支払ってもよいと考える額と実際の運賃との差額)が発生します。
この効果は、単なる利便性の向上に留まりません。沿線地域の立地優位性(他の場所と比べて有利な条件)が高まることで、住宅や企業の新規立地が進み、人口や雇用が増加します。その結果、不動産価値の上昇、沿線企業の収益増加、さらには自治体の税収増加といった経済的利益が生まれます。これが、鉄道整備に伴って発生する開発利益(インフラ整備により生じる不動産価値の上昇益)です。
誰がどのような恩恵を受けているのか
都市鉄道整備によって受益する主体は、主に以下の7つに分類されます。
- 鉄道利用者:所要時間の短縮、乗換回数の減少、定時性の向上といった直接的な恩恵を受けます。
- 鉄道事業者:沿線人口の増加による運賃収入の増大が期待されます。
- 沿線企業:来訪者の増加や雇用確保のしやすさにより、生産効率の向上や収益増につながります。
- 不動産所有者:地価や賃料の上昇により、資産価値が高まります。
- 開発者:開発プロジェクトの採算性が向上し、売却価格や賃料の上昇による利益を得ます。
- 住民:自家用車からの転換による沿道環境の改善や、鉄道があることによる安心感(存在効果)を享受します。
- 国・地方自治体:地価上昇や企業収益の増加に伴う固定資産税や法人税の増収、都市競争力の強化が図られます。
地価上昇という利益の帰着
鉄道整備による効果の多くは、最終的に地価の上昇という形で不動産所有者や開発者に帰着(落ち着くこと)します。居住地の視点で見れば、通勤や通学の負担が軽減されることが立地優位性を高め、その場所を選択する人が増えることで需要が高まり、地価を押し上げます。商業地や業務地においても、来訪しやすさの向上やビジネスの効率化が賃料や不動産価値を高める要因となります。
現在、これらの利益の一部は税金として国や自治体に納められていますが、その全てが鉄道の整備費用に充てられているわけではありません。また、鉄道が整備された場所と納税される場所が異なるケースもあり、受益と負担のバランスが必ずしもとれていない実態があります。
特に、大規模な周辺開発が進んで駅の容量を超えるような場合、鉄道事業者が安全確保のために行う駅改良の費用はきわめて巨額になります。こうした状況下では、まちづくりによる原因者(負荷を与えた側)も含め、幅広い受益者が相応の負担を行う仕組みを検討することには一定の合理性(筋の通った考え方)があると言えます。
未来へ向けた合意形成の第一歩
都市鉄道の整備は、単なる移動手段の提供ではなく、都市の魅力や価値を創出するプロセスです。経営が苦しく、公的支援にも限りがある中で、鉄道事業を維持・発展させていくためには、誰がどのような利益を得ているのかを正しく理解し、公平な費用負担のあり方を模索しなければなりません。
かつての三位一体モデルが持っていた「開発利益を鉄道に還元する」という視点を、現代の社会システムに合わせて再構築することが求められています。それは、運賃という形での負担だけでなく、地価上昇や税収増の一部を鉄道整備に活かすような、新しい官民連携の形をデザインすることに他なりません。
第2回:国内外の成功事例に学ぶ——「上下分離」から「海外の先進制度」まで
開発利益還元の実践:国内外の成功事例にみる負担と共創の形
今回は、こうした幅広い受益者からの支援や開発利益の還元(インフラ整備で得られた利益の一部を建設費等に戻すこと)を具体的に実現した国内外の事例を紹介し、関係者の間でどのように合意形成(意見の一致を図ること)が行われたのかを探ります。
国内における官民連携の先駆け:みなとみらい線と摂津市駅
日本国内においても、プロジェクトの特性に応じて多様な主体が費用を負担した事例は少なくありません。その代表例が、横浜の臨海部を走るみなとみらい線です。
みなとみらい線は、みなとみらい21地区の輸送確保と横浜都心部の一体化を目的に建設されました。このプロジェクトでは、横浜市が鉄道とまちづくりの双方の調整役を担い、強力なリーダーシップを発揮しました。具体的な費用負担の仕組みとして、みなとみらい21線建設費負担協力指導要綱を制定し、開発事業の施行者や土地所有者を負担者として設定しました。負担額は、駅からの距離などを基に算出されたそれぞれの受益(得られる利益)の大きさに応じて按分(割合に応じて分けること)されました。これにより、鉄道事業者や行政だけでなく、開発によって直接的に資産価値が高まる民間主体からも多額の協力を得ることに成功しました。
また、新駅設置の事例として注目されるのが、阪急京都線の摂津市駅です。この駅の整備にあたっては、土地所有者である企業、鉄道事業者、自治体の三者が南千里丘まちづくり構想に関する基本合意書を交わし、役割を明確にしました。建設費用については、当初は市、鉄道、開発者の三者が3分の1ずつ負担する案もありましたが、最終的には市が3分の2、鉄道事業者が3分の1を負担する形となりました。開発者が土地区画整理事業を通じて公共用地を提供していることなどを考慮し、市が開発者の負担分も含めて引き受けたのです。この事例は、まちづくりによる人口増加や利便性向上を前提に、官民が適切な役割分担を行ったモデルといえます。
開発者負担のルール化:多摩ニュータウンと幕張豊砂駅
鉄道整備と大規模な宅地開発が一体となって進められる場合、一定のルールに基づいた負担が行われることがあります。
歴史的に重要なのが多摩ニュータウンルール(正式名称:大都市高速鉄道の整備に対する覚書に基づく多摩ニュータウン関連鉄道に対する助成措置等の運用について)です。このルールでは、開発事業者が鉄道用地を素地価格(開発前の安価な価格)で鉄道事業者に売却し、さらに施行基面下(線路の土台部分)の工事費の2分の1を負担することが定められました。これにより、膨大な建設費の一部が開発利益から還元される仕組みが制度化されました。
比較的新しい事例では、2023年に開業したJR京葉線の幕張豊砂駅があります。この駅の整備では、地元企業であるイオンモールが事業費の50パーセントを負担し、残りを千葉県、千葉市、鉄道事業者の三者で等分しました。大型商業施設の開業に合わせて新駅を設置することで、まちの回遊性(歩き回る楽しさや利便性)が高まり、企業側にも確かな受益があるという共通認識が合意形成の鍵となりました。
海外にみる開発利益還元の制度化
諸外国に目を向けると、より仕組み化された(制度として確立された)還元策が活用されています。地方自治体が地域の実情に応じてこれらの制度を運用しており、日本の今後の議論においても参考になります。
米国のイリノイ州シカゴ市などで採用されているのがTIF(Tax Increment Financing:租税増収分担保融資)制度です。これは、鉄道整備などの事業によって見込まれる将来の固定資産税の増収分を特定し、それを裏付け(担保)として債券を発行し、建設資金を調達する手法です。将来得られるはずの税収を前倒しで建設費に充てることができるため、初期投資が巨額になる鉄道事業に適しています。
英国ロンドンのエリザベスライン(クロスレール計画)では、事業用固定資産税補填法(Business Rate Supplement Act)が活用されました。これは、市域全体の非居住用不動産(オフィスや店舗など)に限定して、時限的(期間を区切った)な増税を行う仕組みです。不動産を収入源とする所有者は、地価上昇の受益を最も受ける主体であるため、受益と負担が概ね一致するという特徴があります。また、同じ英国では、S106(計画義務)やCIL(コミュニティ・インフラ課金)といった、開発者による外部不経済(開発が周囲に与える負荷)の緩和を目的とした負担金制度も併用されています。
韓国のソウル市などでは、大都市圏広域交通管理に関する特別法に基づき、広域交通施設負担金制度が運用されています。宅地開発などを行う開発者に対し、広域的な交通アクセス改善のための費用を課すもので、集められた資金は自治体が選択するインフラ整備に活用できる特定財源(使い道が限定された資金)となります。
合意形成を導く三つのポイント
これらの国内外の事例を分析すると、立場の異なる関係者の間で合意を得るためには、三つの重要な要素があることがわかります。
- 第一に、地元自治体の積極的な関与です。開発利益の還元を実現している事例の多くでは、行政が計画段階からリーダーシップを発揮し、利害関係の調整やまちづくりガイドラインの策定を行っています。行政が仲介役となることで、鉄道側とまち側の連携がスムーズになります。
- 第二に、関係者との協議の仕組み作りです。鉄道沿線に開発計画がある場合、いつ、誰と調整すればよいかを明確にするため、協議会や会議体を設置することが有効です。例えば東京都では、地下鉄駅周辺での都市開発において、鉄道事業者との協議を義務付ける方針を示しています。こうしたルール作りが、結果としてより良いまちづくりにつながります。
- 第三に、受益する内容の明確化です。地価上昇やアクセスの向上といった整備効果を、データに基づき定量的に(数値で具体的に)示すことが、主体が負担を判断するための重要な根拠となります。負担者間の公平感を保ち、フリーライダー(対価を支払わずに利益だけを享受する者)を発生させないという視点が不可欠です。
第3回:未来を拓く「第5のレイヤー」——データが変える都市経営の合意形成
未来を拓くデータの力:エビデンスに基づく都市経営の合意形成
シリーズ最終回となる今回は、都市鉄道の整備効果をいかにして可視化(目に見える形にすること)し、それを関係者間の合意形成(意見の一致を図ること)に役立てるかについて解説します。これまで見てきたように、鉄道が地域にもたらす便益(利益)は多岐にわたりますが、それらは必ずしも目に見える数字として共有されてきませんでした。しかし、近年の高度な分析手法やデータの蓄積により、整備がもたらす価値を定量的(数字を用いた客観的な形)に示すことが可能になっています。
データが証明する整備のインパクト:つくばエクスプレスの事例
鉄道整備が地域にどのような変化をもたらすのかを理解する上で、つくばエクスプレス(TX)の事例は非常に示唆に富んでいます。報告書では、TX沿線自治体と、並行して走るJR常磐線沿線自治体の実績値を比較することで、新線整備の影響を分析しています。
まず人口動態(人口の動き)を見ると、平成18年から令和6年にかけて、TX沿線自治体では人口が顕著に増加しています。例えば、つくば市ではプラス33パーセント、流山市ではプラス38パーセントという大幅な伸びを記録しました。これに対し、JR常磐線沿線自治体では一部を除いて減少傾向にあり、新線整備が居住地としての選択を強力に後押ししたことがデータから読み取れます。
この人口増加は、当然ながら地域の経済価値にも反映されます。公示地価(国が公表する土地の価格)の変化を見ると、TX開業前の2004年から2024年にかけて、駅から1から2キロメートルの範囲を中心に地価が上昇しています。特にまちづくりが先行した守谷市や流山市での上昇が目立ちます。
さらに、自治体の財政基盤である税収にも明確な差が現れています。2005年度を基準とした固定資産税の増加率を見ると、流山市では83.0パーセント増、つくばみらい市では65.6パーセント増となっており、JR常磐線沿線の自治体が限定的な変化に留まっているのと対照的です。単位面積当たりの税額もTX沿線で顕著に伸びており、これは地価(課税標準額)の底上げが税収増に直結したことを示しています。
新駅が創出する拠点価値:摂津市駅の分析
新線だけでなく、既存路線に新しく駅を設ける新駅整備も大きな効果を生みます。阪急京都線の摂津市駅の事例では、開業後の周辺人口や土地利用の変化が詳細に分析されています。
住民基本台帳に基づく分析によると、駅周辺の南千里丘地区の人口は、開業前の平成22年の約200人から、令和5年には約3600人へと急増しました。特筆すべきは年齢構成で、50歳未満の層が全体の72パーセントを占めており、子育て世代の転入が加速したことが分かります。
また、駅から500メートル圏内の人口密度は平成17年から令和2年にかけて1.85倍に上昇しました。これは、駅の設置を契機とした土地区画整理事業により、土地利用が低層建築から中高層建築へと高度化した結果です。さらに、シニア向け住宅の立地に伴い医療・福祉分野の従業人口が約2.5倍に増えるなど、産業構造にも変化をもたらしています。これらのデータは、新駅が単なる停車場ではなく、地域の拠点として機能していることを証明しています。
受益を予測するための科学的手法:DID分析とヘドニックアプローチ
これから新しく鉄道を整備しようとする際、将来の受益(得られる利益)をどのように見積もればよいのでしょうか。報告書では、過去のデータに基づいた2つの主要な分析手法を紹介しています。
1つ目は、夜間人口(その地域に住んでいる人口)の増加効果を測るDID分析(差の差分析)です。これは、鉄道整備が行われたモデル駅と、整備が行われなかった比較対象駅を設定し、両者の整備前後の変化量の差を比較する手法です。地域全体の自然な人口増減(トレンド分)を差し引くことで、純粋に鉄道整備によって生じた効果のみを抽出できるのが特徴です。この手法を用いることで、新駅設置や路線の結節(複数の路線が繋がること)によって、1平方キロメートル当たり何人の人口増が見込めるかを予測できます。
2つ目は、地価上昇効果を算出するヘドニックアプローチです。これは、土地の価格が、駅までの距離、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)、主要駅までの所要時間といった様々な属性の組み合わせによって決まると考える手法です。
この手法を用いたケーススタディでは、ある新線整備によって地価が約9パーセント上昇し、結果として固定資産税収が年間約28億円増加するという推計結果が出ています。また、別の延伸プロジェクトでは地価が約8パーセント上昇し、年間約6億円の税収増が見込まれると算出されました。実績値はこれらの推計をさらに上回る傾向にあり、鉄道整備が周辺の道路や公共施設の価値も相乗的に高めていることが示唆されています。
合意形成の質を高める第5のレイヤー
これらのデータや分析手法を活用することは、これからの都市経営において極めて重要な意味を持ちます。かつての鉄道整備は、しばしば鉄道事業者の熱意や行政の期待といった定性的な(数字に表しにくい)議論に終始しがちでした。しかし、これからはデータという客観的な根拠を基に、誰が、いつ、どの程度の利益を受けるのかを明らかにすることができます。
こうした定量的エビデンス(数値による証拠)は、以下の3つの点で合意形成を後押しします。
第一に、費用負担の公平性の確保です。地価上昇や税収増の予測値を共有することで、開発者や自治体がどの程度の負担を行うべきか、その合理的な根拠を示すことができます。これは、フリーライダー(対価を支払わずに利益だけを得る者)を防ぎ、関係者間の不公平感を解消することに繋がります。
第二に、プロジェクトの優先順位の明確化です。限られた財源の中で、どの路線の延伸やどの駅の改良が最も地域価値を高めるのかを、データに基づいて判断できるようになります。
第三に、主体的なまちづくりの促進です。データによって整備効果が可視化されることで、沿線住民や企業が自分たちの地域の未来を自分たちのこととして捉え、積極的にまちづくりに関与する動機が生まれます。
結論:都市を編み直す新しい羅針盤
都市鉄道は、2050年の脱炭素社会の実現や、人口減少下でのコンパクトな都市構造の構築に欠かせないインフラです。しかし、その整備には巨額の資金と、多くの関係者の理解が必要です。
本シリーズで見てきたように、日米100年の歴史は、鉄道とまちづくりが一体となったときにのみ持続可能な都市が生まれることを教えています。そして現代、私たちはデータを武器に、その一体化をより精緻に、より公平に設計する手段を手にしました。
デジタル技術を活用して整備効果をシミュレーションし、それを基に多様な主体が費用と知恵を出し合う。このプロセスこそが、ソースでも提言されている、これからの都市経営における合意形成の在り方です。データの力で受益の姿を照らし出し、鉄道と都市が共に栄える未来を編み直していくことが求められています。
都市交通と開発利益還元の変遷年表
軌道系交通の黄金期と三位一体モデル(1880 – 1920年代)
この時期は、電力・鉄道・不動産開発が垂直統合されたビジネスモデルが都市を拡大させました。
1888年: 米国で世界初の電動路面電車稼働(スプレーグによる発明)。
1890年代: 米国で路面電車郊外が急増。
1905年: 日本で阪急電鉄の前身(箕面有馬電気軌道)設立。小林一三による鉄道+住宅地開発+商業施設モデルが確立される。
1916年: 米国ニューヨークで全米初のゾーニング(用途地域制)条例が成立。
1919年: 日本で(旧)都市計画法および市街地建築物法が制定される。
制度による分離とモータリゼーションの浸透(1930 – 1950年代)
独占禁止法などの制度介入により、鉄道を支えた内部補助スキームが解体されました。
1935年: 米国で公益事業持株会社法(PUHCA)が成立。電力会社による鉄道部門の強制的切り離しが開始される。
1938年: 日本で陸上交通事業調整法が成立し、交通の戦時統合が進む。
1947年: 日本で独占禁止法および過度経済力集中排除法が成立。
1951年: 日本で電力再編成命令が出され、9電力体制へ移行。地方私鉄の鉄道部門分離が加速する。
1956年: 米国で連邦補助高速道路法が制定され、ガソリン税を原資とする道路信託基金(Highway Trust Fund)が創設される。
公共交通の再発見と受益者負担のルール化(1960 – 1990年代)
自動車依存への反省から、公共交通への予算転用や開発者負担の仕組みが整い始めました。
1968年: 日本で(新)都市計画法が成立し、線引き制度が導入される。
1972年: 日本で多摩ニュータウンルール(正式名称:大都市高速鉄道の整備に対する覚書に基づく多摩ニュータウン関連鉄道に対する助成措置等の運用について)が運用開始。
1973年: 米国で道路信託基金の公共交通(地下鉄・バス等)への転用が全米で解禁される。
1979年: 米国ポートランドで都市成長境界線(UGB)が法的効力を持つ。
1987年: 日本で国鉄分割民営化が実施される。
1990年: 英国で都市農村計画法1990(Town and Country Planning Act 1990)が制定。開発者負担(S106)の根拠となる。
1991年: 米国で連邦効率的陸上交通改善法(ISTEA)が成立。
1996年: 韓国で大都市圏広域交通管理に関する特別法に基づき、広域交通施設負担金制度が開始される。
持続可能な都市と開発利益還元の高度化(2000 – 2020年代)
上下分離方式や容積率緩和を活用した、より柔軟な官民連携スキームが主流となります。
2000年: 日本で交通バリアフリー法が成立。
2006年: 富山ライトレール開業。日本初の本格的上下分離方式が導入される。
2008年: 英国で計画法2008(Planning Act 2008)に基づき、コミュニティ・インフラ課金(CIL)が導入される。
2009年: 英国で事業用固定資産税補填法(Business Rate Supplement Act)が制定され、エリザベスライン整備に活用される。
2014年: 日本で立地適正化計画制度が創設される。
2019年: 日本でウォーカブル推進都市制度が開始される。
2022年: 日本で改正地域公共交通活性化再生法が施行される。
2023年: 宇都宮LRT開業。全線新設のLRTとして上下分離方式による共創ガバナンスを実現。
2025年(予定): 東京都が新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針を改定。地下鉄駅整備において鉄道事業者との協議を義務付ける方針を示す。
このほか、米国では将来の固定資産税増収を財源とするTIF(Tax Increment Financing)制度や、地域一律の負担金を徴収するBID(Business Improvement District)制度などが、開発利益還元の重要な仕組みとして活用されています。
都市鉄道の整備や開発利益の還元、および歴史的な転換点に関連する法律や制度
国内の整備費用・開発利益還元に関する制度
日本における鉄道整備とまちづくりの連携や、受益者負担を定めた主な制度は以下の通りです。
- 多摩ニュータウンルール(正式名称:大都市高速鉄道の整備に対する覚書に基づく多摩ニュータウン関連鉄道に対する助成措置等の運用について) 1972年(昭和47年)に制定。ニュータウン開発に伴う鉄道整備において、開発事業者が用地を素地価格で提供し、施行基面下の工事費の2分の1を負担することなどを定めたルールです。
- P線制度 小田急多摩線や京王相模原線の整備において採用された制度で、日本鉄道建設公団(現・鉄道建設・運輸施設整備支援機構)が建設を担う仕組みに関連します。
- 新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針 東京都が策定。令和7年3月の改定方針では、地下鉄駅とまちが一体となった都市づくりを促進するため、容積率緩和などの適用にあたって鉄道事業者との協議を義務付けるなどの内容が含まれています。
- 上下分離方式 鉄道のインフラ(下部)を公的機関や第3セクターが保有し、運行(上部)を民間事業者が行う方式です。宇都宮LRTや富山ライトレールなどで採用されています。
- 立地適正化計画 2014年に創設された制度で、コンパクトシティの実現に向けて居住や都市機能の誘導を図るための計画です。
歴史的・構造的転換に関連する法律
日米の都市・鉄道史において、ビジネスモデルの変容を強制した重要な法律です。
- 1935年公益事業持株会社法(PUHCA:Public Utility Holding Company Act of 1935) 米国で制定。電力会社に対し、鉄道や不動産など電力事業に直接関係のない事業の切り離しを義務付け、電力×鉄道×開発の垂直統合モデルを解体する契機となりました。
- 過度経済力集中排除法(1947年) 戦後の日本でGHQ主導により制定。独占の排除を目的とし、日本の地方私鉄に多かった電力部門との垂直統合(電燈軌道)が解体される要因となりました。
- 連邦補助高速道路法(1956年) 米国で制定。ガソリン税を原資とする道路信託基金(Highway Trust Fund)を創設し、全米の高速道路網整備を加速させ、モータリゼーションを決定づけました。
海外における開発利益還元の制度
諸外国で導入されている、地価上昇や開発利益をインフラ整備に充てるための法制度です。
- TIF(Tax Increment Financing)制度(米国) 事業実施によって見込まれる将来の固定資産税の増収分を裏付けに債券を発行し、建設資金を調達する仕組みです。
- BID(Business Improvement District)制度(英国など) 特定の地区において、公共サービス向上のために地権者や商業者から一律の負担金を徴収する制度です。
- 事業用固定資産税補填法(Business Rate Supplement Act)(英国) ロンドンのエリザベスラインなどで活用。非居住用不動産に限定した時限的な増税を行い、地価上昇の受益者から費用を回収します。
- 都市農村計画法1990(Town and Country Planning Act 1990)および計画法2008(Planning Act 2008)(英国) 開発者による外部不経済の緩和などを目的とした負担金制度(S106やCIL)を定めています。
- 広域交通施設負担金(韓国:大都市圏広域交通管理に関する特別法に基づく) 宅地開発等を行う開発者に対し、交通アクセス改善のための負担金を課す制度です。