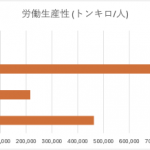一組織では太刀打ちできない複雑な社会課題に、どう挑むべきか。その答えは、多様な主体が依存・共生し合う生態系(エコシステム)の構築にあります。1つの組織が苦境に立たされても、ネットワーク全体で活動を維持し、別の形で再生できる不確実性への耐性。特定のリーダーが支配するのではなく、全員が共に進化し、リソースを最適に配分することで、低コストかつ高度な解決策を生み出すつながりの力に迫ります。
目次
- 1 オープン・イノベーションとエコシステム(Ecosystem)とは
- 2 オープン・イノベーションの学術的定義
- 3 歴史
- 4 事例
- 5 課題
- 5.1 心理的・文化的障壁:NIH症候群
- 5.2 吸収能力(Absorptive Capacity)の欠如
- 5.3 知的財産(IP)の管理とコンフリクト
- 5.4 資源の非対称性と不公平感
- 5.5 ガバナンスと評価の難しさ
- 5.6 OIの課題解決に向けたチェックポイント
- 5.7 分析
- 5.8 課題の解決
- 5.9 心理的・文化的解決:マインドセットのOS更新
- 5.10 組織・構造的解決:吸収能力の強化
- 5.11 法的・契約的解決:知的財産(IP)の柔軟な設計
- 5.12 プロセス的解決:目的の階層化と可視化
- 5.13 社会的・エコシステム的解決:信頼のインフラ構築
- 5.14 OI課題解決のフレームワーク比較
- 5.15 総括
- 5.16 出典・文献
- 5.17 1. オープン・イノベーション(Open Innovation)
- 5.18 エコシステム(Business/Innovation Ecosystem)
- 5.19 オープン・イノベーションとエコシステムの統合
- 5.20 分析
- 6 参考
オープン・イノベーションとエコシステム(Ecosystem)とは
オープン・イノベーションとエコシステムは、もともとビジネスや技術開発の文脈で生まれた言葉ですが、現代の市民活動や地域課題解決においても極めて重要なフレームワークとなっています。
これらは、組織が自前主義を脱却し、外部との相互作用を通じて価値を最大化させるための戦略を指します。
オープン・イノベーション(Open Innovation)
ヘンリー・チェスブロウ教授が提唱した概念で、自社(自組織)の内部と外部のアイデアを組み合わせ、新たな価値を創造することを意味します。
市民活動におけるオープン・イノベーション
従来のNPOや市民活動は、自組織のスタッフと予算だけで課題を解決しようとするクローズド・イノベーションに陥りがちでした。しかし、オープン・イノベーションの視点では以下のように変化します。
- アウトサイド・イン: 外部(大学、企業、異分野の専門家)の知見を取り込み、自組織に欠けている専門性や技術を補完する。
- インサイド・アウト: 自組織で培った独自のノウハウや成功事例を外部に公開し、他地域や他団体に活用してもらうことで、社会全体でのインパクトを広げる。
エコシステム(Ecosystem)
生物学の生態系をビジネスや社会活動に応用した概念です。特定のリーダーがすべてを支配するのではなく、多様な主体が依存・共生し合いながら、全体として一つの循環を形作る構造を指します。
活動を生態系として捉える視点
単発の連携とエコシステムの違いは、その自律性と持続性にあります。
- 多様なプレーヤー: 行政、大企業、スタートアップ、NPO、教育機関、そして意志ある個人がそれぞれの役割を持って存在している。
- 共進化(Co-evolution): 1つの組織の成功が他の組織のメリットになり、互いに刺激し合って成長する関係。
- オーケストレーター: 生態系全体を俯瞰し、異なるプレーヤー同士を繋ぎ合わせるバックボーン組織やコーディネーターの存在が不可欠です。
なぜ単独よりもエコシステムが強いのか
政策学的な分析によれば、エコシステム型の活動には3つの圧倒的な優位性があります。
- リソースの最適配分: A団体は場所を持ち、B社は技術を持ち、C大学はデータを持つ。これらを組み合わせることで、低コストで高度な活動が可能になります。
- 不確実性への耐性: 1つの組織が資金難に陥っても、生態系全体としてネットワークが維持されていれば、活動の火は消えず、別の形での再生が可能になります。
- スケールアップの加速: 成功モデルがネットワークを通じて瞬時に共有されるため、一地域での成功が広域へと波及するスピードが飛躍的に高まります。
市民活動におけるエコシステム形成の課題と対策
| 課題 | 対策 |
| 手柄の取り合い(組織の壁) | コレクティブ・インパクトの手法を用い、共通のKPIを設定して成果を分かち合う。 |
| 情報の非対称性 | デジタルプラットフォームを活用し、誰がどのようなリソース(空き家、スキル等)を持っているか可視化する。 |
| フリーライダーの発生 | ネットワークへの貢献を評価し合う、互酬性の高いルール(社会関係資本の蓄積)を作る。 |
政策学・社会学チームからの総括
オープン・イノベーションとエコシステムの概念を取り入れることは、組織のアイデンティティを境界線(何を自前でやるか)からネットワーク上の位置(誰と何を創るか)へとシフトさせることを意味します。
これからの地域づくりは、強い1つの組織を作るのではなく、面白い活動が次々と生まれる土壌(エコシステム)をどうデザインするかという視点が成否を分けます。
オープン・イノベーションの学術的定義
オープン・イノベーション(Open Innovation)は、2003年にカリフォルニア大学バークレー校のヘンリー・チェスブロウ(Henry Chesbrough)教授によって提唱された概念です。
当初は企業のR&D(研究開発)戦略として定義されましたが、現在では公共政策や市民活動におけるマルチステークホルダーによる協働を説明する重要な理論的支柱となっています。
ヘンリー・チェスブロウによる基本定義
チェスブロウは、オープン・イノベーションを以下のように定義しています。
組織が、自社の技術革新を加速させるために、内部のアイデアと共に外部のアイデアを意図的に利用し、また、自社の技術を市場へ展開するために、内部だけでなく外部の経路(チャネル)も活用すること
この定義の核心は、組織の境界は浸透的(Permeable)であるべきだという認識にあります。
クローズドからオープンへのパラダイムシフト
学術的には、従来のクローズド・イノベーションモデルとの対比で理解されます。
- クローズド・イノベーション:
自組織の優秀な人材だけでアイデアを出し、自前のリソースで開発し、自組織の販路だけで世に出す。自前主義が成功の鍵とされる。
オープン・イノベーション:
外部の優秀な人々とも協力できると考え、自組織にない知見を外から取り入れ、逆に自組織で使い切れないアイデアは外へ提供して他者に活用してもらう。
オープン・イノベーションの2つの方向性
学術的には、知識の流れる方向によって以下の2つ(およびその統合)に分類されます。
- インバウンド(Outside-In):
外部の知識、技術、アイデアを自組織内に取り込み、活動の質を向上させるプロセス。
例:NPOがIT企業のプロボノ(専門家ボランティア)を受け入れ、業務効率化を図る。 - アウトバウンド(Inside-Out):
自組織内で活用しきれていないアイデアや資産を外部に流出させ、他者に活用してもらうプロセス。
例:ある自治体が開発した優れた福祉プログラムをオープンソースとして公開し、他自治体での導入を支援する。
現代的な拡張:公共・社会セクターへの適用
近年、この理論はビジネスの枠を超え、ソーシャル・オープン・イノベーションとして発展しています。
- 知識の民主化: 専門家だけの特権だった解決策の立案に、当事者である市民やユーザーが直接関与する。
- トリプル・ヘリックス(三重らせん)モデル: 大学(知)産業界(経済)政府(政策)の3者が相互作用しながらイノベーションを加速させるという、政策学的なネットワーク理論と融合しています。
批判的論点
学術的にこの定義を扱う際、以下の実行上の課題が指摘されています。
- ノット・インベンティッド・ヒア(NIH)症候群: 他人が考えたアイデアなど受け入れられないという組織内の拒絶反応。これをどう崩すかがガバナンスの焦点となります。
- 吸収能力(Absorptive Capacity): 外部の優れたアイデアを取り入れても、それを受け止めて活用できるだけの基礎体力(専門知識や組織文化)が自組織になければ、イノベーションは起きません。
歴史
オープン・イノベーションという概念は、2003年にヘンリー・チェスブロウによって言語化されましたが、その背景には20世紀後半の産業構造の変化と、知識の爆発的な拡散という歴史的必然がありました。
その変遷を、提唱前の予兆から現代の社会実装まで4つのフェーズで辿ります。
提唱以前(〜1990年代):クローズド・イノベーションの黄金時代
20世紀の大部分において、イノベーションは企業内の秘密の研究所で生まれるものでした。
- ベル研究所モデル: AT&Tのベル研究所のように、優秀な科学者を囲い込み、基礎研究から製品化までを一気通貫で行うスタイルが最強とされました。
- 自前主義の合理性: 外部に知識が乏しかった時代、知識を組織内に独占し、知的財産を鉄壁に守ることが競争優位の源泉でした。
概念の誕生(2000年代前半):チェスブロウによる発見
2003年、チェスブロウが著書『Open Innovation』を出版し、パラダイムシフトを宣言しました。
背景にある4つの浸食要因:
- 熟練労働者の流動性向上: 優秀な人材が転職し、知識が組織外へ漏れ出した。
- ベンチャーキャピタルの台頭: 社外でのアイデア製品化を支援する資金源が生まれた。
- 社外に眠るアイデアの増加: 大学やスタートアップの技術水準が向上した。
- サプライヤーの能力向上: 外部パートナーが設計の一部を担えるようになった。
定義の確立: アイデアの流入(Outside-In)と流出(Inside-Out)の両方を戦略的に行うモデルが定義されました。
多角化と実践(2010年代):IT・デジタル化との融合
インターネットの普及とデジタルツールの進化により、オープン・イノベーションは一部の巨大企業だけでなく、あらゆる組織へ広がりました。
- クラウドソーシングとハッカソン: 不特定多数の知恵を借りる手法が一般化。
- プラットフォーム戦略: 自社を土台(プラットフォーム)として開放し、外部の参加者にその上で価値を創ってもらうビジネスモデル(例:App Store)が主流となりました。
- エコシステムの形成: 単一の提携ではなく、複数の企業・大学・公的機関が相互に依存し合う生態系としての競争が始まりました。
社会的展開(2020年代〜現在):ソーシャル・オープン・イノベーション
現在、この理論はビジネスの枠を完全に踏み出し、複雑な社会課題を解決するためのOSとして活用されています。
- 公共セクターへの適用: 行政が抱える課題をオープンにし、スタートアップや市民団体が解決策を提案するGovTech(ガブテック)の動き。
- リビングラボ(Living Lab): 研究所ではなく、実際の生活圏(街)を実験場とし、住民・企業・行政が共にサービスを創り上げる(共創)スタイル。
- SDGsとコレクティブ・インパクト: 1組織では太刀打ちできない気候変動や貧困などの課題に対し、オープン・イノベーションの枠組みで挑むことが義務に近い認識となりました。
歴史から見る知識の所有権の変化
- 1980年代まで 独占(他人に教えない)
最も優れた研究所を持つこと - 2000年代 交換(外から取り入れる)
最も優れたパートナーを見つけること - 現在 共創(境界をなくす)
最も優れた生態系を育むこと
分析
オープン・イノベーションの歴史は、秘密主義による強さから接続性(つながり)による強さへの移行の歴史です。かつては組織の壁を高くすることが防衛でしたが、現在は壁を低くし、外部のエネルギーをいかにスムーズに取り込むかが生存戦略となっています。
事例
オープン・イノベーション(OI)の事例は、IT業界から製造業、さらには行政や社会課題解決の現場まで多岐にわたります。
成功している事例に共通しているのは、外部のアイデアを単に借りるだけでなく、自組織の強みと掛け合わせて新しいエコシステム(生態系)を構築している点です。
P&G(プロクター・アンド・ギャンブル):コネクト・アンド・ディベロップ
OIの最も古典的かつ成功した事例の一つです。
- 背景: 2000年代初頭、R&D(研究開発)の生産性が低下。自社のみでの開発に限界を感じていました。
- 戦略: 発明の50%以上を外部から取り入れるという目標を掲げ、コネクト・アンド・ディベロップ(C&D)というプラットフォームを構築。
- 成果: ポテトチップスプリングルズの表面に文字を印刷する技術を、イタリアの小さなパン屋から導入して大ヒット。自社開発に固執せず、外部の技術と自社のマーケティング力を統合しました。
NASA(アメリカ航空宇宙局):オープン・チャレンジ
極めて高度な専門知識が必要な領域でも、OIが有効であることを示しました。
- 背景: 宇宙飛行士の健康維持や機材の故障予測など、あまりに複雑で特定の専門家だけでは解決できない課題が山積。
- 戦略: 課題をオンライン上で一般公開し、賞金をかけて世界中の科学者やエンジニアから解決策を募るNASA Tournament Labを実施。
- 成果: 太陽フレアの予測精度を向上させるアルゴリズムが、NASAの内部研究者ではなく、物理学の専門知識を持たない外部の統計学者から提案されるなど、専門外の知見がブレイクスルーを生みました。
星野リゾート:地域との共創
サービス業におけるアウトバウンド型(Inside-Out)に近いOIの事例です。
- 背景: 宿泊施設単体ではなく、地域全体が魅力的でなければ観光客は増えないという課題。
- 戦略: 地域の生産者やガイドなど、外部のプレーヤーと情報を共有し、その土地ならではの体験プログラムを共同開発。
- 成果: 地域の魅力という外部資源を自社の宿泊体験に組み込むことで、高付加価値化に成功。自社の運営ノウハウを地域に提供し、地域全体を潤すエコシステムを形成しました。
宇部興産(現・UBE):技術の外部活用
自社で使い切れない技術を外部に開放し、新たな市場を作った事例です。
- 背景: 優れた素材技術を持っているが、最終製品(コンシューマー向けなど)への展開ノウハウが社内に乏しい。
- 戦略: 技術を独占せず、異なる業界のパートナー企業へライセンス提供や共同開発を積極的に実施。
- 成果: 液晶ディスプレイの材料など、自社だけでは到達できなかった多様な最終製品に自社技術が組み込まれ、収益源の多角化を実現しました。
行政×スタートアップ:Urban Innovation JAPAN
公共セクターが抱える課題をOIで解決する現代的な事例です。
- 背景: 行政の硬直的な入札制度では、スピード感のあるスタートアップの技術を取り入れにくい。
- 戦略: 自治体が抱える現場の課題(例:ゴミの不法投棄監視、窓口の混雑解消)を具体的に公開し、スタートアップと協働で実証実験(PoC)を行う。
- 成果: 神戸市をはじめとする多くの自治体で導入。行政の課題解決スピードが向上すると同時に、スタートアップにとっては公共への導入実績という貴重な資源を得る機会となりました。
事例から見る成功のパターン
- P&G 技術の取り込み
自社のマーケティング・販路という強みを掛け合わせた - NASA 群衆の知恵
宇宙という壁を越え、異分野の専門性を引き出した - 星野リゾート 地域の生態系構築
地域のプレーヤーを競合ではなくパートナーとした - UBE 技術の開放
知的財産を囲い込むのではなく活用させる発想 - UIJ 官民共創
実証実験(PoC)という小さな失敗を許容する枠組み
分析
これらの事例が示すのは、オープン・イノベーションとは単なる外注ではないということです。自組織に足りないピースを外から探し(インバウンド)、自組織に余っているピースを外に活かしてもらう(アウトバウンド)。この情報の非対称性を解消する対話こそが、イノベーションの本質です。
課題
オープン・イノベーション(OI)は、外部の知見を融合させる強力な手法ですが、学術的・実務的には多くの障壁が指摘されています。これらは単なる相性の問題ではなく、組織論や経済学に基づいた構造的な課題です。
主な課題を5つの視点で整理します。
心理的・文化的障壁:NIH症候群
最も頻繁に直面するのが、組織内部の心理的拒絶反応です。
- NIH(Not Invented Here)症候群: 自前で開発したものでなければ信頼できない外部のアイデアを受け入れるのは、自分たちの能力不足を認めることだという誇り(プライド)が、外部知識の吸収を阻害します。
- 変化への抵抗: 外部パートナーとの連携は、従来の仕事の進め方や権限構造を脅かすため、現場スタッフが非協力的な態度をとることがあります。
吸収能力(Absorptive Capacity)の欠如
外部に優れた技術やアイデアがあっても、それを理解し、活用できる能力が自組織になければ、イノベーションは起きません。
- 目利きの不在: 外部の価値を正しく評価できる専門知識が内部にないと、不適切な技術を導入したり、逆に宝の山を見逃したりします。
- 翻訳コスト: 外部(例:大学やスタートアップ)と自組織では、使っている言葉や時間軸、価値観が異なります。これらを繋ぎ合わせる翻訳のプロセスに多大な労力がかかります。
知的財産(IP)の管理とコンフリクト
誰のアイデアかという境界線が曖昧になるため、権利関係のトラブルが起きやすくなります。
- 成果の帰属: 共同開発した成果物の権利をどちらが持つのか、将来の利用範囲をどう設定するかで、法的な争いに発展するリスクがあります。
- 営業秘密の漏洩: 外部と深く連携すればするほど、自組織が守るべきコアなノウハウが流出するリスクも高まります。この開放と保護のバランス(パラドックス)が管理を難しくします。
資源の非対称性と不公平感
特に大企業(あるいは行政)とスタートアップ(あるいは市民団体)の連携で顕著になる課題です。
- 意思決定スピードの差: スタートアップは即決を求めますが、大組織は多層的な決裁ルートがあり、時間差によって機会損失を招きます。
- パワーバランスの偏り: 資金力やブランド力のある強者が、弱者のアイデアや成果を搾取しているように見える非対称性が、信頼関係を壊す要因となります。
ガバナンスと評価の難しさ
従来の管理手法では、OIの成果を正しく評価できません。
- 短期的な効率性との衝突: OIは試行錯誤(プロトタイピング)を伴うため、短期的なコスト対効果(ROI)を求めすぎると、芽が出る前にプロジェクトが打ち切られてしまいます。
- 責任の所在: 複数の主体が関わるため、失敗した際に誰の責任かが曖昧になり、組織としての学習が蓄積されにくい側面があります。
OIの課題解決に向けたチェックポイント
- 文化 外部活用は能力の証という評価制度への転換
- 能力 外部知識を内部化する専任チーム(バウンダリー・スパナー)の配置
- 権利 連携開始前におけるIPポリシーの合意と柔軟なライセンス設計
- 体制 相手のスピード感に合わせた特区的な意思決定フローの構築
分析
オープン・イノベーションの課題の多くは、自立した組織を前提とした従来のマネジメント手法を、そのまま相互依存的なネットワークに持ち込もうとすることから生じています。これらを克服するには、組織の枠を超えた共通の倫理観と、不確実性を許容する新しいリーダーシップへの転換が必要です。
課題の解決
オープン・イノベーション(OI)の課題を解決するには、単に連携を呼びかけるだけでは不十分です。組織の構造、文化、そして制度の3つのレベルで外部と繋がるためのインターフェースを再設計する必要があります。
学術的な解決アプローチと、実務で有効な具体的方策を整理します
心理的・文化的解決:マインドセットのOS更新
- NIH(自前主義)症候群を打破し、組織文化を受容型に変えるためのアプローチです。
目利きの賞賛と評価制度の変更: 自分で発明したことだけでなく、外部の優れた知見を発掘し、自組織の成果に繋げたことを高く評価する人事評価制度を導入します。 - トップダウンのコミットメント: 外部資源の活用は弱さの証明ではなく、戦略的な賢さであるというメッセージを経営層やリーダーが発信し続け、失敗を許容する心理的安全を確保します。
組織・構造的解決:吸収能力の強化
外部のアイデアを正しく理解し、自組織の血肉に変えるための仕組み作りです。
- 専任のバウンダリー・スパナー(境界連結者)の配置: 内部の事情と外部の言語(技術、市場、社会課題)の両方を解する人材を、連携の専用窓口として配置します。
- 出島組織(CVCや特区)の創設: 本体の硬直的なルール(過度なコンプライアンスや多段階決裁)から切り離された、迅速な意思決定が可能な別動隊を組織し、外部パートナーとのスピード感を合わせます。
法的・契約的解決:知的財産(IP)の柔軟な設計
権利関係の不透明さを解消し、双方が安心してリソースを投下できる環境を整えます。
- 共有ではなく利用の設計: 権利を共有(持分比率の決定)にすると、後の活用が複雑になります。むしろ、権利は一方が持ち、もう一方が独占的・非独占的利用権を柔軟に持つ形(ライセンス設計)を推奨します。
- OI契約の標準化: 連携の初期段階で成果物の帰属秘密保持目的外使用の禁止などを定めた柔軟な雛形(オープン・イノベーション促進のための標準契約書など)を活用し、交渉コストを下げます。
プロセス的解決:目的の階層化と可視化
資源の非対称性や評価の難しさを、共通の地図を持つことで解決します。
- ロジックモデルの共有: 短期的な利益(ROI)だけでなく、中長期的な社会変化や組織学習の効果を可視化したロードマップをパートナーと共有します。これにより、目先の失敗で連携が崩壊するのを防ぎます。
- アジャイルな小規模実証(PoC): いきなり巨大な投資をするのではなく、小さく、早く、安く試すプロトタイピングを繰り返し、小さな成功(スモール・ウィン)を積み重ねることで、組織内の懐疑論を払拭します。
社会的・エコシステム的解決:信頼のインフラ構築
個別の組織の努力を超えて、連携を容易にする環境を整えます。
- 中間支援組織(オーケストラター)の活用: 大学、企業、NPOの間に立ち、中立的な立場でマッチングやコンフリクト(対立)の仲裁を行う第三者機関を介在させます。
- 共通プラットフォームの整備: リソース(技術、資金、課題)をオープンにリストアップし、誰もがアクセスできるデジタル空間や物理的なイノベーション・ハブを運営します。
OI課題解決のフレームワーク比較
- 文化(Mind) 評価制度の刷新、トップの宣言
外から学ぶことが誇りになる - 組織(Structure) 出島組織、バウンダリー・スパナー
外部との対話スピードが加速する - 制度(System) IPライセンス、標準契約書
権利トラブルへの不安が解消される - 現場(Process) アジャイル開発、PoC
小さな成功で信頼が蓄積される
総括
オープン・イノベーションの課題解決とは、単に他人の力を借りることではなく、自組織の定義を広げるプロセスです。自社の壁を強固に守ることから、自社を含むエコシステム全体の利益を最大化する方向へパラダイムをシフトさせることが、最終的かつ最も強力な解決策となります。
出典・文献
オープン・イノベーション(OI)とエコシステムは、現代の経営戦略や社会課題解決における共創の核心となる概念です。これらは組織の境界を曖昧にし、外部の知見や資源をいかに自律的な循環に取り込むかという問いに対する学術的回答です。
1. オープン・イノベーション(Open Innovation)
自社の内部資源だけでなく、外部のアイデアや技術を積極的に活用し、価値を創出するプロセスです
- Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. (邦訳:『オープン・イノベーション:組織を越えたネットワークが価値をつくる』英治出版)
解説: オープン・イノベーションという言葉を定義した、歴史的な原典。クローズドなR&D(研究開発)の限界を指摘し、技術が社外へ流出したり、社外から流入したりするファンネル(漏斗)モデルを提唱しました。 - Chesbrough, H. W. (2006). Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. (邦訳:『オープン・ビジネスモデル:知財を利益に変える戦略』翔泳社)
解説: 技術そのもの以上に、外部と繋がるためのビジネスモデルの設計がいかに重要かを論じています。 - 西口泰夫 (2014). 『オープン・イノベーションの本質』日経BP.
解説: 京セラ元社長の視点から、日本企業がなぜOIで苦戦するのか、そしてどう組織文化を変えるべきかを実践的に論じています。
エコシステム(Business/Innovation Ecosystem)
単なる連携を超え、多様な主体が相互に依存し、共進化(共に進化)する動的な生態系を指します。
- Moore, J. F. (1993). “Predators and Prey: A New Ecology of Competition.” Harvard Business Review.
解説: ビジネス・エコシステムという概念を世界で最初に提唱した論文。企業を単一の産業に属するものとしてではなく、生態系(Ecosystem)の一部として捉える視点を提供しました。 - Adner, R. (2012). The Wide Lens: What Successful Innovators See That Others Miss. (邦訳:『ワイドレンズ:イノベーションを成功させるエコシステム戦略』東洋経済新報社)
解説: エコシステム論の現代的なバイブル。自社の成功は、連携するパートナー(共同イノベーター)や普及の担い手が成功して初めて達成されるという相互依存のリスクを分析しています。 - Iansiti, M., & Levien, R. (2004). The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability. (邦訳:『キーストーン戦略:エコシステムのビジネス戦略』ダイヤモンド社)
解説: エコシステムの健全性を維持する中心的存在キーストーン(要石)の役割を定義しました。
オープン・イノベーションとエコシステムの統合
両概念を社会課題解決や地域創生に適用するための文献です。
- Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). “Towards a Theory of Ecosystems.” Strategic Management Journal.
解説: バリューチェーン、プラットフォーム、エコシステムの違いを厳密に定義し、現代の複雑な市場構造を解明した学術的に非常に重要な論文です。 - Chesbrough, H. W., & Di Minin, A. (2014). “Open Social Innovation.” in The Oxford Handbook of Innovation Management.
解説: OIの概念を社会課題解決(ソーシャル・イノベーション)に適用。これが後のコレクティブ・インパクトの理論的背景の一部にもなっています。
分析
これらの文献を統合すると、中間支援組織(コーディネーター)が果たすべき役割が見えてきます。
- OIの視点: 組織外から新しい知を流入させる(バウンダリー・スパニング)。
- エコシステムの視点: 参加者が共倒れにならないよう、相互依存関係を管理し、キーストーン(要石)としてプラットフォームを維持する。
- チェスブロウ なぜ一社で開発してはいけないのか?
知識の流動性 (Knowledge Spillover) - アドナー パートナーが失敗するとどうなるか?
相互依存のリスク (Adoption Chain Risk) - イアンシティ エコシステムの健全性をどう保つか?
キーストーン戦略 (Keystone Strategy)
注意
以上の文書はAI Notebook LM が生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。
[先頭に戻る]