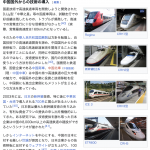脱炭素社会の実現に向け、企業の排出量評価が進んでいますが、現在の評価軸は車両の燃費改善などの「部分最適」に偏りがちです。本連載では、環境経済学の視点から、見えない環境負荷を可視化する手法や「社会的共通資本」の考え方を解説します。土地利用の集約化やインフラの維持管理を含む、ライフサイクル全体での多面的な検証こそが、公共交通や物流の真の価値を浮き彫りにすることを論じていきます。
脱炭素社会の実現に向け、企業の排出量評価が進んでいますが、現在の評価軸は車両の燃費改善などの「部分最適」に偏りがちです。本連載では、環境経済学の視点から、見えない環境負荷を可視化する手法や「社会的共通資本」の考え方を解説します。土地利用の集約化やインフラの維持管理を含む、ライフサイクル全体での多面的な検証こそが、公共交通や物流の真の価値を浮き彫りにすることを論じていきます。
目次
- 1 第1回:なぜ市場は「環境」を守れないのか? ―― 負の外部性と市場の失敗
- 2 第2回:見えない価値に「値段」をつける ―― ピグー税から社会的共通資本(SCC)へ
- 3 第3回:スコープ3の「盲点」 ―― 燃費削減だけで本当に十分か?
- 4 第4回:真の環境貢献度とは何か ―― インフラ、土地利用、そしてレジリエンス
- 5 参考
第1回:なぜ市場は「環境」を守れないのか? ―― 負の外部性と市場の失敗
皆さんは日々の生活の中で、買い物をしたりサービスを利用したりする際、その価格がどのように決まっているか考えたことはあるでしょうか。私たちが支払う代金は、通常、その商品を作るための原材料費や人件費、そして企業の利益などが組み合わさって決まります。これを経済学では市場メカニズム(需要と供給のバランスによって価格が決定される仕組み)と呼びます。
外部性
しかし、この便利な市場メカニズムも、環境という大きな存在を前にすると、うまく機能しなくなることがあります。今回の連載では、環境経済学という学問の視点から、私たちが直面している脱炭素社会への課題を紐解いていきます。第1回は、なぜ市場は環境を守ることが苦手なのかという点について、外部性(取引の当事者以外に影響が及ぶこと)という概念を中心に解説します。
経済学において、環境は限られた資源の一つとして捉えられます。きれいな空気や水、安定した気候は、私たちが経済活動を営む上での土台です。しかし、これらの環境資源は、多くの人が無料で利用できる公共財(誰もが利用でき、一人が使っても他人の利用を妨げにくい性質を持つもの)としての側面を持っています。ここに、環境問題の難しさが潜んでいます。
例えば、ある工場が製品を製造する過程で二酸化炭素を排出しているとします。この二酸化炭素は地球温暖化の原因となり、将来的に気象災害や農作物の不作といった形で社会全体に損害を与えます。これを経済学では負の外部性(ある主体の活動が、対価のやり取りなしに他者に不利益を与えること)と呼びます。
市場の失敗
問題は、この損害費用が製品の価格に含まれていない点にあります。工場側からすれば、二酸化炭素を排出しても直接的な費用が発生しないため、排出を抑制する経済的な動機が働きません。結果として、社会全体で見た時の最適な量よりも多くの製品が生産され、多くの排出が行われてしまいます。これが市場の失敗(市場に任せておくと、社会的に望ましい資源配分が達成されない状態)と呼ばれる現象です。
この時、企業が負担しているコストを私的費用(原材料や人件費など、企業が帳簿上で支払う費用)、社会全体が受けている損害も含めたコストを社会的費用(私的費用に外部費用を加えた総コスト)と呼びます。環境経済学の大きな役割は、この乖離を埋めることにあります。
外部性の内部化
現在、日本を含む世界各国で進められているカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにすること)の取り組みは、この外部性をいかにして市場に取り込むかという挑戦でもあります。このプロセスを外部性の内部化(外部費用を当事者のコストとして価格に反映させること)と言います。
日本の政策
日本の政策に目を向けると、GX推進法(グリーントランスフォーメーションを推進するための法律)に基づき、炭素賦課金や排出量取引といったカーボンプライシング(炭素に価格をつける仕組み)の導入が進められています。これらの施策は、これまで見過ごされてきた環境負荷というコストを、経済の循環の中に組み込もうとするものです。
日本の政策担当者も、急激なコスト上昇が企業の国際競争力や国民生活に与える影響を十分に考慮しています。そのため、段階的な導入や、得られた資金を企業の技術開発支援に充てるなど、経済成長と環境保全を両立させるための配慮がなされています。市場の失敗を認めつつ、それを補完するための制度設計が慎重に進められているのが現状です。
しかし、現在の評価軸にはまだ課題が残されています。多くの議論は、工場や自動車から直接出る排出量に集中しがちです。しかし、環境負荷はもっと多層的です。一つの製品が作られ、運ばれ、使われ、最後には廃棄されるまでの一連の流れ、すなわちライフサイクル(製品の生涯)全体で見ると、評価は変わってきます。
例えば、自動車単体の燃費性能を改善することは重要ですが、それだけで社会全体の排出量が劇的に減るわけではありません。人々がどのように移動し、どのように街が作られているかという、より大きなシステムの影響を強く受けるからです。公共交通への転換が議論される理由も、単に乗り物の種類を変えること以上に、社会全体のエネルギー効率を高めるという側面があるからです。
次回の記事では、こうした見えない価値をどのように評価し、宇沢弘文教授が提唱した社会的共通資本(社会全体で管理・維持すべき大切なインフラや自然)という考え方が、現代の環境政策にどのような示唆を与えてくれるのかを詳しく見ていきたいと思います。
市場は万能ではありませんが、適切なルール(制度設計)を加えることで、環境を守るための強力な力になり得ます。私たちは今、環境を経済の外側に置くのではなく、経済の仕組みそのものの中に環境を正しく位置づける時代に生きています。
参照元・出典:
- 環境省 カーボンプライシングの動向について
- 経済産業省 GX実現に向けた基本方針
主要文献:
第2回:見えない価値に「値段」をつける ―― ピグー税から社会的共通資本(SCC)へ
第1回の記事では、環境問題がなぜ起こるのかという経済的な仕組みについて、負の外部性(ある活動が対価なしに他者に不利益を与えること)という視点から整理しました。今回は、その見えない環境負荷や価値をどのように数値化し、社会のルールに反映させていくべきかという点について考えを深めます。
価値を測る
経済活動において、価格がついていないものは存在しないものとして扱われがちです。きれいな空気や豊かな森に値札がついていなければ、道路を作るためにそれらを壊しても、経済計算の上では損失がゼロと見なされてしまいます。これを防ぐためには、環境が持つ多面的な価値を貨幣単位で測定する環境評価(市場で取引されない環境の価値を経済的に見積もること)というプロセスが必要です。
環境経済学には、こうした価値を測るための手法がいくつか存在します。代表的なものに仮想評価法(アンケートを用いて、環境保護のためにいくらまでなら支払ってもよいか、あるいはいくら受け取れば損失を受け入れるかを尋ねる手法)があります。これにより、これまで無視されてきた自然の価値を、他の政策経費と同じ土俵で比較することが可能になります。また、トラベルコスト法(その場所を訪れるために費やした交通費や時間から環境の価値を推計する手法)やヘドニック価格法(環境の良し悪しが不動産価格に与える影響を分析する手法)といったデータに基づくアプローチも、政策立案の現場で活用されています。
こうした評価を行うのは、費用便益分析(政策にかかる費用と、それによって得られる社会全体の利益を比較して妥当性を判断すること)の精度を高めるためです。日本の公共事業評価においても、環境への影響は考慮の対象となっています。しかし、従来の評価の多くは、対策を実施するための直接的なコストに焦点が当たりやすく、その対策が長期的にもたらす広範な便益(社会的な利益)を十分に網羅できているとは言い難い面もあります。
社会共通資本(SCC)
こうした背景の中で、私たちが立ち返るべき重要な視点があります。それは、経済学者の宇沢弘文教授が提唱した社会的共通資本(ゆたかな社会を維持するために、社会全体で管理・運営すべき共通の財)という考え方です。社会的共通資本は、大きく3つの範疇に分けられます。1つは大気、森林、河川といった自然環境。2つめは道路、交通機関、水道などの社会的インフラ。そして3つめが教育や医療、金融といった制度資本です。
社会的共通資本の考え方の際立った特徴は、これらを単なる市場の商品としても、国家の所有物としても扱わない点にあります。これらは各分野の専門家集団によって、職業的規範に基づき信託(信頼して管理を委ねること)されるべきものと定義されています。例えば、森林を管理するのは利益を優先する企業でも、一律の規則を課す行政でもなく、森林の生態系を熟知した専門家であるべきだという論理です。
公共交通への適用
この視点を公共交通に当てはめてみましょう。公共交通は単なる移動の手段ではなく、都市の構造を規定し、人々の移動の権利を保障し、同時に環境への負荷を低減させるための社会的共通資本です。現在の日本の政策でも、地域公共交通活性化再生法(地域公共交通の維持と発展を目指す法律)などを通じて、公共交通を維持するための努力が続けられています。政策担当者は、人口減少社会におけるインフラ維持の難しさを十分に認識しており、効率性と公共性のバランスを模索しています。
スコープ3の限界とLCA
しかし、現在のスコープ3(原材料調達から廃棄までのサプライチェーン全体の排出量)の議論や環境評価において、公共交通が持つ多面的な価値が十分に評価されているでしょうか。例えば、鉄道やバスなどの公共交通が維持されることで、自家用車による移動が減り、交通事故や渋滞という社会的費用(社会全体が負担する損失)が抑制されます。さらに、駅を中心に居住地が集約されることで、インフラの維持管理コストが低下し、社会全体のエネルギー効率が高まります。
環境経済学の視点から言えば、公共交通への投資は単なる補助金ではなく、負の外部性を減らし、正の外部性(ある活動が対価なしに他者に利益を与えること)を最大化するための賢明な社会支出です。しかし、日本の現在の評価基準では、こうした空間構造の変容による長期的な排出削減効果や、維持管理におけるLCA(ライフサイクルアセスメント:製造から廃棄までの環境影響評価)の観点が、十分に指標化できていない部分もあります。
政府もこうした課題に対し、無策ではありません。例えば、国土交通省が進めているコンパクト・プラス・ネットワーク(生活機能を拠点に集約し、公共交通で結ぶ都市計画)という方針は、まさに土地利用の集約化による持続可能な社会を目指したものです。評価手法の確立には膨大なデータと時間が必要であるため、一歩ずつ慎重に進められているのが実情です。
私たちに求められているのは、こうした政策の方向性を、環境経済学の理論的な枠組みで補強し、より説得力のある評価軸として提示していくことです。第3回、第4回では、この理論を具体的な実務やサプライチェーンの議論にどのように接続していくか、特にLCA全体での検証という観点から論じていきます。
環境を経済の仕組みの中に取り込むことは、単に税金をかけたり規制を作ったりすることではありません。私たちの社会にとって何が大切なのかを数値で見える化し、それを守るための最適な仕組みを構築することです。社会的共通資本という考え方は、効率性のみを追求する経済のあり方に対し、人間らしいゆたかな生活を送るための知恵を授けてくれます。
参照元・出典:
- 国土交通省 公共事業評価の概要
- 内閣府 社会的共通資本としての医療・介護
主要文献:
第3回:スコープ3の「盲点」 ―― 燃費削減だけで本当に十分か?
これまでの連載では、環境経済学の視点から市場の失敗を整理し、社会的共通資本としての公共交通の重要性について触れてきました。連載第3回となる今回は、現在多くの企業が取り組んでいるスコープ3(原材料調達から廃棄までのサプライチェーン全体の排出量)の開示に焦点を当てます。この取り組みが広まる中で見えてきた、現在の評価軸の課題と、今後求められる多面的な検証について考えていきます。
現在、多くの日本企業は、国際的な基準であるGHGプロトコル(温室効果ガス排出量の算定と報告に関する国際的な基準)に基づき、自社の活動だけでなく、取引先や製品の使用段階、廃棄段階までを含めた排出量の算定を進めています。特にスコープ3は、サプライチェーン全体を網羅するため、企業の気候変動対策の透明性を高める上で大きな役割を果たしています。
インプルーブへの偏り
しかし、経済学的な視点から現状を分析すると、現在の評価軸には一つの偏りが見受けられます。それは、製品単体の燃費向上や、動力源を化石燃料から電気へ切り替えるといった対策、いわゆる改良(インプルーブ:技術的な効率改善によって排出を減らすこと)に評価が集中している点です。
例えば、物流業界を例に挙げましょう。トラックのエンジンをより効率的なものに変えたり、電気自動車に置き換えたりすることは、スコープ3の数値を下げる上で直接的な効果があります。これは企業にとって計算しやすく、成果を可視化しやすい手法です。一方で、移動そのものを効率化して走行距離を減らす回避(アボイド:不要な移動の削減や輸送距離の短縮)や、トラックから鉄道や船舶へと輸送手段を切り替える転換(シフト:より環境負荷の低い移動・輸送手段へ移行すること)の効果は、現状の算定ルールでは適切に評価されにくい傾向にあります。
ASIフレームワーク
交通政策や環境経済学の世界では、これらの3つの頭文字をとったASIフレームワーク(回避・転換・改良の3段階で交通の環境負荷を低減する考え方)が標準的な視点として用いられています。このフレームワークに照らすと、現在の企業の評価軸は、3番目の改良に大きく依存しています。しかし、社会全体の排出量を大幅に削減するためには、1番目の回避と2番目の転換の価値を正当に見積もることが不可欠です。
ここで重要になるのが、公共交通による社会減少(ある主体の活動が社会全体の排出量を抑制する効果)という考え方です。ある企業が自社の社員の通勤や製品の配送を自家用車や個別輸送から公共交通へ転換した場合、その企業のスコープ3の数値には反映されますが、それによって社会全体でどれだけの排出が回避されたかという貢献度は、現在の開示制度では主役にはなり得ません。
LCAへ
さらに、評価をより厳密にするためには、LCA(ライフサイクルアセスメント:製品の製造、輸送、使用、廃棄に至る一生を通じた環境影響の評価)の視点を、車両だけでなくインフラそのものにも広げる必要があります。これは、インフラ建設・維持管理に伴う排出量も考慮に入れるべきだという議論です。
例えば、自動車走行のための道路を1キロメートル建設し、それを数十年にわたって維持管理するために消費されるエネルギーやコンクリートから出る二酸化炭素は膨大です。一方で、既存の鉄道網を活用し、輸送の集約化(荷物や人をまとめて運ぶことで効率を高めること)を図ることは、新たなインフラ建設に伴う排出を抑えることにつながります。現在の評価軸は、走行時の排出量というフロー(一定期間の変化量)には敏感ですが、インフラというストック(蓄積された資産)の維持に伴う排出という視点は、まだ発展途上の段階にあります。
日本の政策
日本の政策に目を向けると、環境省や経済産業省は、SBT(科学的根拠に基づいた温室効果ガス削減目標)の認定を推進し、企業の脱炭素経営を後押ししています。日本の施策の強みは、産業界の実情に即して、サプライチェーン排出量の算定ガイドラインを整備し、実務レベルでの普及を図ってきた点にあります。政策担当者は、急激な制度変更が企業の負担にならないよう配慮しつつ、国際的な潮流に合わせた透明性の確保に努めています。
ただし、日本の制度設計においても、公共交通への転換がもたらす広範な社会的な便益(社会全体が得る利益)を、企業の排出削減貢献分としてどう認めていくかという点は、今後の議論の焦点となるでしょう。これは、単なる計算手法の問題ではなく、企業の努力をどこまで認めるかという評価の哲学に関わる問題でもあります。
全体最適へ
強調したいのは、部分最適(個別の企業や製品だけの効率化)の積み上げが、必ずしも全体最適(社会システム全体としての効率化)につながらない可能性があるという点です。車両を電気自動車に変えても、それによって交通渋滞が悪化し、社会全体での移動効率が低下してしまえば、環境への貢献度は相殺されてしまいます。
土地利用の集約化、つまり駅を中心としたコンパクトな街作りが進むことで、人々の移動距離が短くなり、公共交通の利便性が高まる。こうした社会構造の変化がもたらす排出削減効果は、個別の企業のスコープ3の計算式には現れにくいものですが、それこそが持続可能な社会を支える基盤となります。
次回の最終回では、これらの課題を踏まえ、2026年以降に日本が目指すべき新しい評価軸のあり方について論じます。エネルギー消費効率や土地利用の集約化、そしてライフサイクル全体を見据えた、多面的な検証による真の環境貢献度の正体について、具体的な展望を示したいと思います。
参照元・出典:
- 環境省 サプライチェーン排出量算定の考え方
- グリーン購入ネットワーク(GPN) LCAの重要性について
主要文献:
- 越智正昭著 ライフサイクルアセスメントの基礎 日刊工業新聞社
- 日本交通政策研究会編 交通のライフサイクル分析 成山堂書店
- GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Standard
第4回:真の環境貢献度とは何か ―― インフラ、土地利用、そしてレジリエンス
これまでの連載では、環境経済学の視点から市場の失敗を捉え直し、現在のスコープ3評価が抱える技術偏重の課題について論じてきました。最終回となる今回は、これまでの議論を統合し、2026年以降の日本において、どのような多面的な評価軸が必要とされるのか、その具体的な展望を提示します。
私たちが目指すべき環境貢献度の評価は、単にテールパイプ(車両の排気口)から出る二酸化炭素を計測することに留まってはなりません。より広い視点、すなわち空間構造やインフラの維持管理、さらにはエネルギー消費効率の分母そのものを問い直す必要があります。
土地利用の集約化
まず第一に考慮すべきは、土地利用の集約化がもたらす環境便益です。経済学において、都市の密度とエネルギー効率には強い相関があることが知られています。公共交通を軸としたコンパクトシティ(生活機能が集約された都市構造)は、移動距離そのものを短縮するアボイド(回避)の効果を最大化します。これは、個別の車両がどれほど低炭素化されたかという評価を超えて、社会全体の活動をいかに低炭素な構造に組み替えるかという問題です。
現在の日本の政策である立地適正化計画(居住や福祉、商業などの施設を誘導し、公共交通と連携させる計画)は、まさにこの構造改革を目指したものです。政策担当者は、地方都市における人口減少とインフラ維持のジレンマを解決するため、土地利用の集約化に向けた制度設計を丁寧に進めています。しかし、こうした都市構造の変化がもたらす長期的な排出削減効果は、現在の企業のスコープ3算定においては、評価の対象外となっています。
インフラの建設・維持管理を含むLCA
第二に、インフラの建設・維持管理を含むLCA(ライフサイクルアセスメント:製品やサービスの全生涯にわたる環境負荷評価)の徹底です。車両の製造や走行時の負荷だけでなく、それを支えるインフラストラクチャという資本ストック(蓄積された資産)の維持に伴う排出量を可視化しなければなりません。
例えば、広大な道路網を維持するためには、大量のアスファルトやコンクリート、そして多大な維持補修作業が必要です。これに伴う二酸化炭素排出量は、フロー(日々の移動)の陰に隠れた、社会の埋没炭素(インフラに固定化された排出量)です。公共交通、特に既存の鉄道網の活用は、単位輸送量あたりのインフラ維持コストおよび環境負荷を劇的に抑制します。このインフラ維持管理コストの差を、環境貢献度の一部として算定する仕組みが求められます。
移動価値による評価
第三に、エネルギー消費効率を評価する際の「分母」の再定義です。現在の多くの評価は、一台の車両がどれだけの燃料を消費したかという視点に基づいています。しかし、環境経済学の観点から真に問うべきは、一定のエネルギーを投入して、どれだけの移動価値(輸送人数・距離)を創出したかという点です。
自家用車は一人の移動に一トン以上の鉄を動かしますが、公共交通は数百人を一括して運びます。この圧倒的な集約効率(資源の利用効率を極大化すること)こそが、公共交通の持つ本質的な環境性能です。2026年、日本が世界のサステナビリティ開示をリードするためには、こうした空間効率や輸送密度を組み込んだ、新しい効率性指標の確立が不可欠です。
日本への適用
日本の施策についても、弱点に対する配慮はなされています。例えば、地方における公共交通の維持が困難な地域では、一律に公共交通への転換を強いるのではなく、デマンド型交通(予約制の乗り合いバスなど)やシェアリングエコノミーの活用が模索されています。これは、画一的な基準を押し付けるのではなく、地域の実情に合わせた多様な解(マルチモーダルなアプローチ)を認めるという、日本の政策担当者の現実的な配慮の現れです。
今後、日本が国際的な評価基準に提案すべきは、企業の枠を超えた社会減少のクレジット化(社会全体の排出を減らした貢献を数値として認めること)です。ある企業が、物流をトラックから鉄道へモーダルシフト(輸送手段の転換)したり、社員の通勤を公共交通に促したりする行動が、自社の排出量削減だけでなく、社会全体のインフラ負荷や土地利用効率にどう貢献したかを、多面的に検証する枠組みです。
そのためには、システムダイナミクス(複雑な事象を要素間の相互作用として捉える手法)を用いた社会シミュレーションが有効です。移動手段の選択、インフラの維持、都市の配置、これらが互いに影響し合う動的なシステムとして環境負荷を捉えることで、初めて真の環境貢献度が明らかになります。
4回にわたる連載を通じて、環境経済学という学問が、単なる数字の遊びではなく、私たちがどのような社会に住みたいかを決めるための羅針盤であることをお伝えしてきました。環境貢献度を多面的に検証するということは、私たちの社会をより合理的で、より人間らしい、社会的共通資本に守られたゆたかな場所にすることに他なりません。
2026年、脱炭素の議論はさらに深化します。部分的な技術改善に一喜一憂するのではなく、社会の骨格を成す公共交通や土地利用という大きな構造を見据え、真に持続可能な未来に向けた一歩を、皆さんと共に踏み出せることを願っています。
参照元・出典:
主要文献:
- 宇沢弘文著 社会的共通資本 岩波新書
- 日本交通政策研究会編 地域公共交通の統合的評価 成山堂書店
- OECD The Environmental Performance of Public Transport
ご愛読いただきありがとうございました。今回の議論が、日本の物流・交通の未来を担う皆様の戦略的な一助となれば幸いです。
注意
以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。
参考
スコープ3が拓く日本の未来 ― 物流・公共交通・まちづくりの新・経済学
環境社会学から読み解く公共交通の外部性-日欧米英比較
宇沢弘文博士 「社会的共通基本」を元に鉄道政策を考える