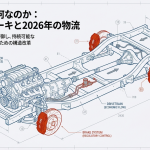江戸時代の「関係性」を基盤とした商いのあり方を現代の地域経済再生のヒントとして考察しています。特に、縁日や門前町で行われていた商売は、一見客をその場で稼ぎ切るのではなく、「お馴染みさんとのご縁を作る」ことに主眼が置かれており、この持続的な関係構築が長期的な収益につながっています。また、神社の布教活動を担った御師が、旅行と店舗の誘客を組み合わせたクーポン(「ご来店の際は蕎麦1枚サービス」など)を提供したことが、日本の団体旅行の起源となったという具体的な事例も紹介。現代のイベント中心で一時的な収益を追う商売ではなく、お客様の心の機微を読んで喜びを提供し、愛情をもって商売を楽しむ老舗のような「ソリューション営業」の重要性を再評価しています。
江戸時代の「関係性」を基盤とした商いのあり方を現代の地域経済再生のヒントとして考察しています。特に、縁日や門前町で行われていた商売は、一見客をその場で稼ぎ切るのではなく、「お馴染みさんとのご縁を作る」ことに主眼が置かれており、この持続的な関係構築が長期的な収益につながっています。また、神社の布教活動を担った御師が、旅行と店舗の誘客を組み合わせたクーポン(「ご来店の際は蕎麦1枚サービス」など)を提供したことが、日本の団体旅行の起源となったという具体的な事例も紹介。現代のイベント中心で一時的な収益を追う商売ではなく、お客様の心の機微を読んで喜びを提供し、愛情をもって商売を楽しむ老舗のような「ソリューション営業」の重要性を再評価しています。
2025年11月25日 中部経済新聞 中経論壇に執筆コラム掲載。(ネットは有料記事です、ぜひ紙面をご覧ください)
動画概要
音声概要
このコラムの音声概要をお聞きいただけます。
江戸時代の「縁」の経済学:御師・縁日・福引に学ぶ!現代ビジネスが失った「関係性」と「お馴染みさん」の育て方
記事イメージ