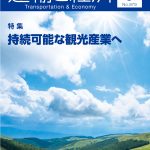目次
なぜ今、「社会的共通資本」なのか?
地方の鉄道路線が次々と廃線の危機に瀕し、都市部では交通渋滞が深刻化する現代において、私たちは交通インフラをどのように評価すべきでしょうか。そのヒントになるのが、経済学者・宇沢弘文が1974年に提唱した社会的共通資本(Social common capital : SCC)という概念です。宇沢博士は、社会的共通資本を次のように定義しました。
「一つの国ないしは特定の地域に住むすべての人々が、豊かな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持するための社会的装置」
これは、鉄道のような社会を支える基盤が経済の道具だけではなく、人々の生活の質や文化、そして社会の持続可能性そのものを規定するという考え方です。
SCCは、大きく分けて以下の3つの資本から構成されます。
- 自然環境
- 大気、水、生態系など。これらは社会の持続可能性の基盤となります。
- 社会的インフラ
- 道路、鉄道、港湾など。すべての人々がアクセスできることが重要です。
- 制度的資本
- 教育、医療、司法、そして交通事業が持つべき専門的規範など。社会の公正性や安定性を支える無形の制度です。
この記事では、鉄道という交通インフラが、単なる経済活動の道具ではなく、社会のあり方を根底から規定する「社会的共通資本」であることを、「効率性」と「公共性」という対立軸から考えます。
自動車交通への偏重と「社会的費用」の外部化
SCCの視座から見た日本の交通政策における大きな課題は、自動車依存がもたらす膨大な社会的費用を内部化することを一貫して拒絶してきた点にあります。自動車交通が引き起こす公害、交通事故、交通渋滞、騒音、自然環境の破壊といった負の側面は、「社会的費用」として市場価格に適切に反映されることなく、社会全体が負担する「外部不経済」として構造的に放置されてきました。[音声概要]
特に、かつての道路特定財源制度は、「受益者負担の原則」を援用し、実際にはその歳入構造と使途を自動車利用者の便益に著しく偏らせました。この制度は、自動車交通が生み出す甚大な社会的費用を無視するだけでなく、鉄道やバスといった公共交通との間に決定的に不公正な競争環境を創出しました。これは、非自動車利用者を含む社会全体が自動車利用者の生み出す外部不経済を実質的に補助する逆進的な構造であり、宇沢博士が重視した「所得配分の公正性」に明確に反するものでした。
鉄道が担っている「社会的共通資本」としての役割と変質
鉄道は単に人や物を運ぶ移動手段ではありません。それは、宇沢博士の言う「豊かな人間社会を維持する」ための基盤であり、社会的共通資本そのものでした。鉄道が担っている公共性には、主に2つの特徴があります。
- 普遍的サービス理念 かつて国鉄が掲げた「全国一律のサービス提供」という理念は、採算が取れない地域にも鉄道網を維持することを意味しました。これは、社会的共通資本が持つべき「すべての人々が利用可能であるべき社会的装置」という理念と完全に合致しており、地域間の公正性を担保する役割を果たしていました。
- 都市機能との相互作用 鉄道という交通インフラは、駅を中心に都市を形成し、人々の住む場所や働く場所を規定します。このように、交通インフラは都市の土地利用と深く結びつき、人々の「社会的、経済的、文化的、人間的活動を規定する、決定的な役割」を果たしています。鉄道は、日本の都市構造と国民のライフスタイルを支える基盤なのです。
鉄道の公共性はどう変質したのでしょう?
民営化の論理:「効率性」の追求とその影
1987年の国鉄民営化は、「巨額の赤字」と「非効率な経営体質」を解消するために必要だとされました。競争原理を導入し、採算性を重視することで、経営を健全化するというのが推進論の根幹でした。しかし、この論理は社会的共通資本の理念とは多くの点で対立していました。
効率性の絶対化
民営化の議論では、収益性や費用便益分析(CBA)といった経済的な効率性が絶対的な基準とされました。その結果、非採算路線の維持や雇用の確保といった公共性は、二の次として扱われました。
制度的資本の解体
国鉄が公的な存在として担ってきた「全国一律の公共輸送サービスの提供」という職業的・専門的な規範は、民営化によって営利を目的とする株式会社の「商業的規範」に置き換えられました。これは、社会的共通資本の最も重要な基盤である「制度」を意図的に変質させる行為でした。この「制度的SCC」の解体は、地方の路線や駅といった「物理的SCC」の維持を困難にし、「人間的に魅力ある社会を持続的に、安定的に維持する」ことを不可能にする深刻な影響をもたらしたのです。
社会的費用の無視
民営化によって不採算路線が切り離された結果、多くの地方住民は移動の自由を制限され、生活基盤そのものが揺らぎました。これは地域社会が負担する目に見えないコスト、「社会的費用」です。具体的には、自動車交通が引き起こす公害、交通事故、交通渋滞といった、市場価格には反映されないコストを指します。この社会的費用は、民営化の議論において十分に考慮されることはありませんでした。
効率性と公共性の対立は、政策評価基準から
評価軸の対立:国鉄末期、民営化推進論、そしてSCCの視点
民営化をめぐる議論では、何を「善」とし、何を「問題」とするかの評価軸そのものが大きく変化しました。その変遷を以下の表で整理します。
| 評価基準 | 国鉄末期の管理規範 | 民営化推進論(反SCC) | SCCが要求する規範 |
| 優先目標 | 全国一律の輸送、公共性 | 経営の効率化、採算性確保 | 効率性(持続可能な経営)と 公正性(普遍的サービス)の両立 |
| 主要指標 | 輸送量、路線網維持 | 収益、B/C比(部門別) | 社会的費用、環境影響、MCAによる多角的価値 |
| 制度的資本の変質 | 職業的規範、公的使命 | 商業的規範、株主利益 | 専門家による厳格な公共的規範の再確立 |
この評価軸の変化は、政策を評価する手法にも表れています。特に「効率性指標(CBA)」と、SCCの考え方に近い「多基準分析(MCA)」の違いは決定的です。
| 比較項目 | 効率性指標(CBA: 費用便益分析) | 多基準分析(MCA) |
| 目的 | 資源配分の効率性 | 効率性(持続可能な経営)と公正性(普遍的サービス、非市場的価値)の統合的評価 |
| 評価の志向 | 市場の短期的な収益性や政治的な短期利益を重視 | 長期的な公共性、安全性、専門的倫理を最優先 |
| 評価対象例 | 利用者便益の最大化(時間短縮など) | 移動の権利、環境の持続可能性、長期的な社会の安定 |
| 課題 | 公正性や環境の価値を矮小化しがち。 政策を効率性に偏重させる構造的バイアスを持つ。 |
定量化が難しく、政治的な影響力においてCBAに劣後しがち。 |
なぜCBAが政策決定の場で強い影響力を持ったのでしょうか。それは、CBAが生み出す「便益費用比(B/C)」のような指標が定量的でわかりやすく、政治的・メディア的に利用しやすかったからです。一方で、MCAが評価しようとする「公正性」や「長期的な安定」は数値化しにくいため、議論の場で後回しにされがちでした。この評価手法の偏りが、効率性への偏重という構造的なバイアスを生み出したと考えられます。
失われた公共性を取り戻し、持続可能な交通政策を再構築するためには?
社会的共通資本に基づく交通政策の再構築
ここまでの分析から、日本の交通政策、特に国鉄民営化の過程は、CBAに代表される効率性指標への偏重により、宇沢博士が提唱した「効率性と公正性の統合」を達成できなかったことが明らかになりました。その結果、制度的資本は解体され、地方の交通システムは衰退に直面しています。
宇沢博士のSCC理論を現代の交通政策に適用するためには、以下の4つの方向性が考えられます。
- インフラ評価システムの見直し 費用便益分析(CBA)への偏重を是正し、環境や公平性といった多角的な価値を評価する多基準分析(MCA)の役割を大幅に強化します。これにより、経済効率性だけでは測れない社会全体の利益を政策決定の中心に据える必要があります。
- 制度的共通資本の再建 民営化によって曖昧になった公共交通の役割を再定義し、採算性を超えた「公共サービス提供義務(Universal Service Obligation: USO)」(採算性に関わらず、全国民に最低限のサービスを保障する義務)を法的に明確化します。市場原理だけではなく、公共性に基づく「職業的規範」が守られる制度的枠組み(例:公共的使命・倫理を評価基準に組み込んだ公的資格制度の強化、専門家組織による監査、市場の短期的な収益変動から公共サービスを守る恒常的な財源保障)を再構築することが不可欠です。
- 自動車交通の「社会的費用」の内部化 渋滞や環境破壊といった自動車交通が生み出す「社会的費用」を、炭素税やロードプライシング(都心部への乗り入れ課金)といった形で価格に反映させます。そして、その収益を公共交通ネットワークの維持・強化、および交通弱者支援に充当することで、交通システム全体の公平性と持続可能性を高めます。
- コンパクトシティ戦略との連携 人口減少社会において、公共交通を都市計画の核と位置づけ、土地利用と交通計画を一体化させます。これは、かつて国鉄が自然に果たしていた交通インフラを都市形成の中心とする思想への回帰とも言えます。公共交通への投資は単なるコストではなく、地域社会を持続させるための必須の投資であり、地域経済を活性化させる起爆剤として捉え直す視点が求められます。
私たちが考えるべき社会インフラの未来と課題
重要なのは、「効率性」と「公共性」のバランスをいかに取るか、という問いです。鉄道のような社会インフラを市場原理だけに委ねると、短期的な採算性が優先され、地方での投資不足(経済学で言う市場の失敗)や、環境破壊・地域格差など「社会的費用」の深刻な問題を引き起こすことが明らかになりました。
社会インフラの未来は、短期的な「効率性」の追求から、長期的な豊かさを生み出す「社会的共通資本」の維持・拡充へと、その評価軸を転換できるかにかかっています。そのために、私たちには次のような課題が託されているのです。
- 学術的課題
- SCCが持つ環境、公平性、レジリエンスといった非市場的な価値を、政策議論の場で説得力を持つ形で定量化するMCA指標を開発すること。
- 政策的課題
- 人口減少が進む地域において、社会的共通資本への投資がもたらす長期的な乗数効果に関する実証研究によってその効果を示し、政策提言の確実性を高め、持続可能な財源確保の論拠を構築すること。
引用文献
- 名著探訪 社会的共通資本 – 宇沢弘文 著|書籍探訪|書籍の寄贈・紹介|企画調査委員会, 2025年10月6日に閲覧
https://www.cpij.or.jp/com/gp/books_review/312books01.html - インフラ事業の多元的な効果の統合的評価手法に関する考察, 2025年10月6日に閲覧
http://jsrsai.jp/Annual_Meeting/PROG_61/A07-1.pdf
- 投稿タグ
- #academic, #AI, #Car dependency, #Economy, #Politics, #Voice, #Wikipedia, #厚生経済