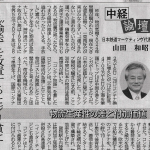音声概要をお聴きいただけます
 Notebook LM でWikipedia記事を学習して生成したラジオ番組風音声概要をこちらからお聴きいただけます。
Notebook LM でWikipedia記事を学習して生成したラジオ番組風音声概要をこちらからお聴きいただけます。
Wikipediaの記事
インテリジェント・アーバニズムの原則 (PIU) のWikipedia記事は、英語やルーマニア語など4カ国語の記事があり、英語版から日本語記事が翻訳されました。
関連項目としてニューアーバニズム(英語版の内容が豊富)やスマートグロースなども参考になりますが、10の原則が何を網羅しているのかを明記しているページは他に見当たりませんでした。
持続可能な都市モビリティ計画 (SUMP) と見比べると、SUMP がこの PIU の原則(住民参加、効率性、地域統合等)に則っていることが見えてきます。
都市の機能って何?
 ArchitectPlanner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons PIU 10原則のアイコン
ArchitectPlanner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons PIU 10原則のアイコン
インテリジェント・アーバニズムの原則 (PIU) では10の原則を挙げています。「原則7:機会マトリックス」は、後述の共存で触れる創造や活力、そして個人の成長など人が変化する多様な「機会」を人々にもたらすことが都市の機能だと位置付けています。集まるから便利なだけではなく、集まるから生まれる・変われるということです。若者が都会を目指したがるのも、ここなのかと改めて気付かされます。そして PIU ではその機会を立場が弱い方々にも与えることに腐心しています。ここは、SUMP で繰り返し言われる「弱い立場の人の話を聞け」という思想に繋がっています。
特に「原則4:共存」では、個人からご近所、多様な人が集う都市まで、それぞれが求める孤独や交流から新たな創造や活力、住民の幸せを創り出すという発想が見えます。人と人が交流するには、人為的に人が歩いて行き交う場が必要になるところが、交通を考えるきっかけになっていますし、都市計画が多様な住宅を必要とする理由が見えてきます。友情や恋が生まれやすい、一人で瞑想に耽る、そんな場所まで建築家が考えて都市設計しているとなんて、驚きです。そして「都市領域の場所」として通勤・通学圏を一括して捉える考え方は、まさにSUMPの「交通圏」を計画対象にする考えに繋がっています。
そして「原則6:人間の尺度」では、歩ける範囲に買い物や医療などのサービスがあれば、自動車依存にならない街が作れる。これが人間性を豊かにもするということが書かれています。これもSUMPの人間中心の考えにつながります。
また、はっとさせられたのは「原則8:地域統合」の石蹴り遊びのところ。これって国道沿いに点々とロードサイド店が点在する風景そのものです。なるほど、放っておくとこうなっちゃうという典型が日本全国に拡がっているいることが見えて、恥ずかしくなってきます。
このように10の原則には、都市計画やまちづくりに必要な項目を、ハード面だけでなく住民の幸せや成長に至るまで考えを巡らしており、これがスマートグロースやSUMPなどにも反映されていることがわかります。建設して理論を検証・統合してさらに改善していくということを積み上げてきた体系や構造が見えてきます。これを理解すると、街の見え方も変わりますね。ぜひ Wikipedia の記事もご覧ください。
10の原則
- 原則1:自然とのバランス
- 原則2:伝統とのバランス
- 原則3:適正技術
- 原則4:共存
個人のための場所、友情の場所、家族の場所、近所の場所、コミュニティの場所、都市領域の場所 - 原則5:効率性
- 原則6:人間の尺度
- 原則7:機会マトリックス
- 原則8:地域統合
- 原則9:バランスの取れた動き
- 原則10:制度の透明性
- 投稿タグ
- #academic, #Urban design, #Voice, #Wikipedia, #都市計画