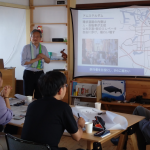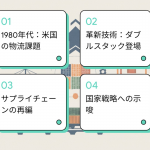日本都市計画学会が開催する2025年度全国大会(第60回論文発表会)に参加しました。「都市を知らねば交通は語れない」という64年前のジェイコブズ女史からのお叱りもあり、ともかく学ばねばという気持ちからお伺いしました。先生方を始め素晴らしい方々とお会いでき、大変勉強になりました。
日本都市計画学会が開催する2025年度全国大会(第60回論文発表会)に参加しました。「都市を知らねば交通は語れない」という64年前のジェイコブズ女史からのお叱りもあり、ともかく学ばねばという気持ちからお伺いしました。先生方を始め素晴らしい方々とお会いでき、大変勉強になりました。
開催は2025年11月15日・16日、芝浦工業大学 豊洲キャンパス。発表論文169本、シンポジウム、ワークショップ8、エクスカーション2という大きな大会でした。滋賀県や鳥取県からの発表もあり「懐かしい」と思えたり、調整池の水辺空間の発表に溜池ファンの血が騒いだりもしましたが、交通関係のトラックもしっかりとありました。都市工学は土木の工学的な分野と、多様なステイクホルダーが協力して作り上げるので社会学に重なり、全体最適の効率性を実現するため経済学にも重なります。ここは交通でも同じです。初参加の気づきは
- 交通計画より規模が大きいが、交通と同様に現場のプロが不足している(交通と連携させたい)
- エリアプラットフォーム、アーバニストなど交通計画に比べ市民参画が進んでいる(交通側が学べる)
- 交通が原因で衰退した地域を地域・空間の魅力で改善しようとしている(交通と連携させたい)
- 都市計画らしく次の40年と学会の長期ビジョンを策定中(交通側が学べる)
遅ればせながら交通も市民参画をはじめています。11月30日のフォーラムにぜひご参加ください。
音声解説
論文予稿集(公開)を学習し、Notebook LM で生成
都市計画学会 最新研究が示す場所と心都市の未来像
動画解説
研究概要紹介
169本の論文をAI NoteboookLM に学習させ、以下の研究概要紹介を生成しました。誤りが含まれている恐れがあるため、あくまで構造理解のヒントとして活用いただき、興味を持った分野は記載されている論文を確認されるようお願いいたします。
現代の都市は、人口減少と高齢化、気候変動の激化、急速なデジタル化、そして地域コミュニティの変容といった、複雑で相互に連関する課題に直面しています。これらの課題に対応するため、都市計画・建築分野の研究アプローチは多様化・学際化しています。従来の物理的な空間計画に留まらず、ビッグデータを活用した人流解析、気候変動への適応策としてのグリーンインフラ、コミュニティ主導のガバナンスモデル、さらには都市と人間の関係を問い直す新たな理論的視座まで、研究領域は大きく拡張されています。
この記事では、近年の都市計画論文予稿集に掲載された学術論文を横断的に分析し、現代の都市計画・建築研究における主要なテーマ、方法論の潮流、そして今後の研究課題を体系的に整理することを目的としています。具体的には、以下の5つの主要な研究領域に沿って議論を紹介します。
- 都市の骨格をなす「都市構造と土地利用の再編」
- ビッグデータを活用した「交通・人流解析の深化」
- 気候変動と災害リスクに対応する「環境・防災とレジリエンス」
- 都市のソフト面を支える「コミュニティとガバナンス」
- 研究のフロンティアを探る「新たな理論的視座」
現代の都市計画・建築研究が、データ解析による客観性の追求と、個々の生活体験や文化的価値といった質的側面への再注目という、一見矛盾する二つの潮流の狭間で、新たな統合的アプローチを模索している様相が見えてきます。複雑化する都市問題の全体像を俯瞰し、今後の研究と実務の方向性を展望するための一助となれば幸いです。
1. 都市構造と土地利用の再編
都市の骨格を形成する「都市構造」と「土地利用」に関する最新の研究動向を分析します。人口減少社会という大きなパラダイムシフトの中で、都市をいかに再編し、持続可能なものとしていくかは、あらゆる個別分野の研究を理解する上での基盤となります。コンパクトシティ政策の具体的な効果検証から、都市機能の集積・制御手法、土地利用規制の弾力的な運用実態に至るまで、マクロな視点から都市の変容を捉える研究群を概観することは、現代の都市計画が直面する根源的な課題を理解する上で戦略的に重要です。
コンパクトシティ政策の実践と課題
近年のコンパクトシティ政策の中核をなす立地適正化計画は、その効果と課題が多角的に検証されています。特に、居住誘導区域(居誘区域)や都市機能誘導区域(都誘区域)の設定が、住民の行動や土地市場にどのような影響を与えているかが注目されています。
ある研究では、東京都市圏を対象にパーソントリップ調査データを分析し、居誘区域が必ずしも自動車利用の抑制に繋がっていない実態を明らかにしました(論文22)。これは、制度設計と住民の実際の交通行動との間に乖離が存在することを示唆します。また、地価への影響を分析した研究では、非線引き都市において居誘区域の内側で地価が上昇する傾向が見られる一方、線引き都市では明確な影響が見られないことが報告されています(論文23)。これは、地域の都市構造や市場特性によって制度の効果が異なることを示しています。
さらに、市街化調整区域における地区計画制度との関係性も重要な論点です。調整区域に設定された地区計画が、立地適正化計画の誘導方針と矛盾し、市街化を抑制すべき区域で事実上の市街地拡大を許容している事例が指摘されています(論文52, 54)。これは、異なる制度が意図せぬ形で相互に影響し、計画全体の整合性を損なうリスクを示しています。
主要な知見
以上の分析から、立地適正化計画を巡る研究は以下の重要な知見を提供しています。
- 行動変容の限定性:区域設定が、特に自動車利用の抑制といった期待された交通行動の変容に直結していない実態が明らかになった。
- 効果の文脈依存性:制度がもたらす地価への影響は、都市の線引き制度といった基盤的条件によって異なり、一律の効果は期待できない。
- 制度間の不整合リスク:他の土地利用制度との整合性が欠如した場合、コンパクトシティの理念が実質的に損なわれる危険性が指摘されている。
都市機能の集積・制御に関するアプローチ
都市機能の集積と制御は、都市の活力と効率性を左右する重要なテーマであり、多様なアプローチから研究が進められています。
政策的アプローチの代表例として、フランクフルト市の高層建築物計画(HHEP)が挙げられます(論文1)。同計画は、経済発展を優先しつつも、スカイラインの形成や公共交通との連携、居住機能の確保といった複合的な目標を掲げています。その特徴は、法定計画(Bプラン)策定の前段階に準備手続きを標準化することで、民間開発を都市全体のビジョンに沿って誘導しようとする先進的な試みにあります。
一方、計量的なアプローチでは、パーソントリップ調査データを用いて、活動タイプ(就業、商業、公共)ごとに都市活動拠点(UAC)を識別する手法が開発されています(論文15)。この研究は、活動ごとに人々の移動距離や集積パターンが異なることを明らかにし、画一的ではない、機能に応じた拠点の捉え方を提案しています。
また、コロナ禍後の社会変化を捉える研究として、東京都心部における企業の移転動向を分析したものがあります(論文49)。分析によれば、コロナ禍においても都心部への企業集積の傾向は継続しており、特に情報通信業などで広域からの移転が見られるなど、産業構造の変化が都市機能の配置に影響を与えていることが示唆されています。
これらの研究は、都市機能の配置力学が複合的であることを示しています。フランクフルトの事例は政策的ビジョンによるトップダウンの誘導可能性を示す一方、計量分析は活動タイプごとに異なる集積原理が存在することを明らかにしています。さらにコロナ禍後の動向は、マクロ経済や産業構造の変化が、計画者の意図を超えて都市構造を再定義する強力な要因であり続けることを示唆しています。
土地利用規制の弾力的運用とその影響
厳格な土地利用規制を維持しつつ、地域のニーズに柔軟に対応するための弾力的な運用も、国内外で重要な研究テーマとなっています。
国内では、第一種低層住居専用地域における特例許可施設(建築基準法第48条)の立地動向が分析されています(論文20)。この研究は、許可された施設の多くが幹線道路沿いや用途地域の境界に立地する傾向を明らかにし、許可プロセスで指摘される交通課題との関連性を示唆しています。また、人口減少下においても工業系の市街地が拡大し、その中で住宅建築が許容される地区計画が存在する実態も報告されており(論文51)、産業振興と居住環境の間の緊張関係が浮き彫りになっています。
国外の事例としては、デンマークのコンバージョンビレッジ(CV)制度が注目されます(論文34)。これは、厳しい土地利用規制が敷かれている農村地域において、集落の持続に必要な開発を戦略的に許容する制度です。事例分析からは、同制度が住宅開発の促進や環境保全といった地域ごとの開発方針に応じて柔軟に運用されている実態が明らかになり、日本の「小さな拠点」形成に向けた示唆を与えています。これらの研究は、規制緩和が地域にもたらす便益と、無秩序な開発や環境悪化といった潜在的リスクの双方を慎重に評価する必要があることを示しています。
本章で概観した都市構造と土地利用の再編は、計画論的な枠組みの変容を示すものですが、その実効性は最終的に市民の行動変容に依存します。次章では、このミクロな行動レベルでの実態を、最新のデータ解析がいかに解き明かしつつあるかを探ります。
2. データ駆動型アプローチによる交通・人流解析の深化
本章では、交通系ICカードやスマートフォンから得られる位置情報(GPS)といった新たなビッグデータを活用し、交通計画や人流解析を深化させる研究の最前線を分析します。従来の大規模調査では捉えきれなかった、より詳細かつ連続的な市民の移動行動や滞在パターンを解明するデータ駆動型アプローチは、交通サービスの評価や都市空間の設計に新たな次元をもたらします。このアプローチが、人々の行動原理をより深く理解し、精緻な都市・交通計画を実現する上で持つ戦略的重要性を明らかにします。
新規交通モード(LRT)導入の効果検証
2023年に開業した宇都宮ライトレール(LRT)は、その導入効果が多角的に検証されており、データが交通政策評価に果たす役割を示す好例となっています。交通系ICカードデータを用いた分析では、「乗車自体を目的とする本源需要」というユニークな需要の存在が明らかにされました(論文40)。この需要は派生的な移動需要とは異なり、開業初期に特に多く、時間とともに減少する傾向が示され、新規交通機関導入時の特有の需要動態を定量的に捉えています。
また、子育て世帯を対象としたアンケート調査では、LRTの導入が子どもの私事目的の外出や親の飲酒目的の外出における自動車送迎行動に影響を与えていることが示されました(論文45)。特にLRT沿線に居住する世帯で自動車送迎が減少し、LRT利用へと転換する傾向が見られ、LRTが特定の生活行動において自動車依存を低減させる可能性を示唆しています。
さらに、日英のLRT事業評価手法を比較した研究では、英国の評価マニュアルが地域経済への波及効果(ワイダーエコノミックインパクト)を費用便益分析に組み込んでいる点が指摘されています(論文46)。宇都宮LRTの事例にこの手法を試算した結果、大きな便益が算出され、日本の事業評価手法が持つ課題と拡張の可能性を提示しました。これらの研究は、LRTが単なる交通手段の追加に留まらず、市民の楽しみや生活行動、さらには地域経済にまで複合的なインパクトをもたらすことを浮き彫りにしています。
多様な移動行動の定量的把握
位置情報データを活用することで、従来は質的にしか語られなかった多様な移動行動の定量的把握が可能になっています。以下に、近年の主要な研究成果をまとめます。
- 滞留を伴う散策行動「ランブリング行動」の分析(論文8)
目的: 滞留と散策を一体的に「ランブリング行動」と定義し、その発生と都市環境との関連性を解明する。
データ: 携帯電話GPSログ。
主要な発見: 高密度な商業・アメニティ施設が集積するエリアでランブリング行動が発生しやすい一方、中密度エリアでは店舗数だけでなく、その影響力や歩行環境の質が行動に影響を与えることを示した。 - 大規模再開発が周辺地域の回遊行動に与える影響(論文7)
目的: 大規模再開発の前後で、来訪者の滞在パターン別に周辺地域での回遊行動がどう変化したかを明らかにする。
データ: GPS人流データ。
主要な発見: 歩行者デッキや地下通路の整備が周辺の回遊性を向上させ、再開発地区が通過動線として機能するようになった。一方で、施設内で長時間滞在するワーカーが増え、周辺での滞在時間は減少する傾向も見られた。 - 通勤交通手段と生活行動の関連性(論文14)
目的: 通勤時の交通手段が、退勤時の立ち寄り行動や休日の外出行動にどのような影響を与えるかを分析する。
データ: 位置情報データ。
主要な発見: 鉄道利用者は勤務地周辺で多様な立ち寄り行動を行う一方、自動車利用者は居住地近辺での立ち寄りが多い。また、鉄道利用者は立ち寄りの習慣が休日の外出頻度と関連しており、日常の移動パターンが生活様式全体に影響することを示唆した。 - バスターミナル利用者のアクセス・イグレス圏の分析(論文41)
目的: 高速バスが発着するバスターミナル(BT)利用者の、BTへのアクセス(行き)およびBTからのイグレス(帰り)における移動圏の空間的特徴を明らかにする。
データ: GPSデータ。
主要な発見: BT利用者の滞在先は、BT周辺の商業施設だけでなく、乗り換え拠点となる主要駅周辺にも集積する傾向がある。アクセス圏とイグレス圏の形状は非対称であり、都市構造や交通ネットワークの影響を受けることを示した。 - COVID-19前後の都心部における滞在時間の変化(論文42)
目的: 交通系ICカードデータを用いて、COVID-19のパンデミック前後で高松市都心部における滞在時間がどのように変化したかを分析する。
データ: 交通系ICカード利用履歴データ。
主要な発見: コロナ禍を経て、平日の長時間滞在(通勤・通学等)の割合が減少し、3時間程度の中時間滞在の割合が増加した。これは働き方の変化等が都心部での時間の使い方に影響した可能性を示唆している。
総じて、これらの研究は都市内の移動行動分析が、単純な起点-終点(OD)トリップの把握から、個人のライフスタイルや都市空間の質と深く結びついた、文脈依存的で多目的な「滞在」や「回遊」といった行動の質的側面の解明へとシフトしていることを示しています。これは、交通計画が単なる効率性の追求から、都市体験の豊かさを創出する空間計画へと接近している潮流を反映しています。
地域交通サービスの評価と課題
データ駆動型アプローチは、既存の地域交通サービスの評価にも新たな視点を提供します。特に、利用者数が伸び悩むデマンド交通については、住民がサービスにどのような価値を見出しているかを理解することが重要です。
ある研究では、デマンド交通導入地域でアンケート調査を行い、住民が認識する価値とサービス評価との関連性を分析しました(論文43)。その結果、住民は「いざという時に利用できる安心感」や「移動の選択肢が確保されていること」といった、直接的な利用価値以外の価値を高く評価していることが明らかになりました。一方で、実際のサービス評価においては、「運行時間」や「予約方法」といった利便性に対する満足度が低いことも指摘されています。このギャップは、デマンド交通のサービス設計において、単なる効率性だけでなく、住民の潜在的な安心感や期待にいかに応えるかという視点が不可欠であることを示唆しています。
データによって明らかになった人々の行動変容が、都市の環境や防災といった物理的側面とどのように相互作用するのかという問いは、計画論における次の重要な論点です。次章では、この相互作用を解明し、都市のレジリエンス強化を目指す研究動向に焦点を当てます。
3. 環境・防災と都市のレジリエンス強化
本章では、気候変動への適応と激甚化する自然災害への備えという二つの喫緊の課題に対し、都市のレジリエンス(回復力・強靭性)強化に貢献する研究動向を分析します。環境と防災は、もはや個別の政策課題としてではなく、土地利用、インフラ整備、コミュニティ形成といったあらゆる都市計画の基盤となるべきものです。災害リスク評価から脱炭素化に向けた建築・エネルギー計画、そしてグリーンインフラの多面的価値に至るまで、持続可能で安全な都市を実現するための研究が持つ戦略的重要性を論じます。
災害リスク評価と復興計画
災害に関する研究は、リスクの定量的評価からコミュニティ主体の防災力強化まで、多岐にわたるテーマで進められています。
- リスク評価と人口動態: 全国スケールで洪水浸水想定区域における1995年から2020年までの人口増減を分析した研究は、多くの浸水想定区域で人口が増加しているという衝撃的な事実を明らかにしました(論文50)。特に市街化区域での人口増が顕著であり、土地利用規制や防災まちづくりが、水害リスクと居住実態の乖離という深刻な課題に直面していることを示しています。
- 避難計画: 津波避難シミュレーションの分野では、歩行者と自動車の混在を考慮し、時間経過とともに変化する交通状況下での動的な最適避難経路を導出するモデルが開発されました(論文47)。この研究は、画一的な避難計画ではなく、リアルタイムの状況に応じた柔軟な避難誘導の可能性を示しており、情報通信技術(ICT)の活用とも連携しうる先進的なアプローチです。
- 復興プロセス: 東日本大震災後の防災集団移転団地における居住実態調査からは、復興プロセスにおける住宅選択の動態が明らかになりました(論文12)。多くの被災世帯が自力再建宅地を選択する一方で、災害公営住宅では一般募集や移住者を受け入れることで入居率を維持している実態が報告されています。これは、災害公営住宅が将来的に地域の移住者受け入れの受け皿として機能する可能性を示唆しています。
- 地域防災力: 歴史的な防災施設である「砂留」の保全活動が、住民の防災意識や行動に与える影響を分析した研究は、コミュニティ主体の防災活動の重要性を浮き彫りにしました(論文48)。砂留の認知や保全活動への賛同が、災害への危機感や共助意識を高め、最終的に避難行動にも繋がるという構造が示され、地域の歴史的資産が現代の防災力を育む核となりうることを示しています。
3.3. 脱炭素化に向けた建築・エネルギー計画
都市の脱炭素化は、建築物単体から地域全体のエネルギーシステムに至るまで、統合的なアプローチが求められています。
建築分野では、建物のライフサイクル全体でのCO₂排出量(LCCO₂)削減が重要なテーマです。札幌都心部を対象に、市街地更新に伴う建築物の木造化によるLCCO₂削減効果を評価した研究では、木造化が特に建設段階でのCO₂排出量削減に大きく貢献することが示されました(論文9)。
エネルギー計画の分野では、再生可能エネルギー熱(太陽熱、地中熱、下水熱)のポテンシャル評価が進められています(論文27)。この研究は、札幌都心部において、特に下水熱が高いポテンシャルを持つことを明らかにし、地区の用途構成や建物特性に応じた最適な熱供給システムの構築が重要であると論じています。
さらに、再エネの導入拡大には社会的な合意形成が不可欠です。再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電事業を対象とした法的考察の研究では、漁業者や地域住民といった関係者の権利利益を法的にどのように位置づけ、合意形成プロセスにおける正当性を確保するかが論じられています(論文24)。これは、技術的な課題だけでなく、制度的・社会的な枠組みの構築が脱炭素化の鍵であることを示しています。
3.4. グリーンインフラの多面的価値と管理手法
グリーンインフラ(GI)は、防災・減災機能だけでなく、環境、景観、ウェルビーイング向上といった多面的な価値を持つものとして再評価されています。その価値を最大化するための評価・管理手法に関する研究も進展しています。
水辺の倒景(水面に映る景色)に対する緑地管理の影響を数理モデルで解明した研究や、公園緑地の雨水浸透機能を土地被覆の種類や利用頻度に応じて精緻に評価する手法を提案した研究など、GIの持つ特定の機能を定量的に評価する試みがなされています。また、企業緑地の第三者認証(SEGES, ABINC)がESG情報開示とどのように関連しているかを分析した研究は、GIへの取り組みが企業の社会的評価に繋がる構造を明らかにしました。
以下の表は、近年のグリーンインフラ関連研究が明らかにした価値や手法をまとめたものです。
研究テーマ
- 水辺の倒景に対する緑地管理の影響(論文16)
草木の繁茂が倒景の視覚的魅力を急激に減少させることを数理モデルで示し、景観維持のための緑地管理の重要性を定量化した。 - 企業緑地の第三者認証(SEGES, ABINC)とESG情報開示の関係(論文29)
第三者認証の取得が、企業の非財務情報報告書における環境への取り組みとして積極的に開示されている実態を明らかにした。 - 都市公園の芝生管理に関する評価フレームワークの提案(論文30)
従来の画一的な管理目標ではなく、「目標ランク」と「実態ランク」を比較することで、実務に即した柔軟な管理評価を可能にした。 - 公園緑地の雨水浸透機能の新たな評価手法の提示(論文31)
土地被覆(芝、裸地、植栽等)や利用頻度(踏圧)を考慮することで、より実態に即した雨水浸透能力の評価を可能にした。 - 日常的に利用可能な調整池(柏の葉アクアテラス)の生活・文化的価値の解明(論文32)
兼用調整池が、「日常的憩い機能」「自然観察機能」「学びと賑わい創出機能」といった複合的な価値を住民に提供していることを示した。
これらの研究は、GIが持つ多様な価値を可視化し、その効果的な計画・管理手法を開発することの重要性を示しています。
レジリエントな都市の実現には、こうしたハードなインフラ整備だけでなく、それを支え、活かすための社会的な仕組み、すなわちコミュニティの力や新たなガバナンスのあり方が不可欠です。次章では、この都市のソフト面に焦点を当て、その最新動向を探ります。
4. コミュニティとガバナンスの新たな展開
本章では、都市の社会的な側面、すなわち地域コミュニティのあり方、市民参加の計画プロセス、そして官民連携による新たな都市経営(ガバナンス)の手法に関する研究動向を分析します。物理的なインフラ(ハードウェア)としての都市から、それを運営し、価値を創造する仕組み(ソフトウェア)としての都市へという視点の転換は、現代の都市計画論において極めて戦略的な重要性を持っています。市民参加、地域活性化、包摂的な福祉、エリアマネジメントといったテーマを通じて、都市の活力を内側から生み出すためのアプローチを探ります。
市民参加と協働の計画プロセス
市民参加は、単なる意見聴取から、計画の立案・実施における協働のプロセスへと進化しています。
愛知県長久手市を対象に、10年以上にわたる行政計画と市民参加の関係性の変遷を追跡した研究(論文35)は、市が条例制定などを通じて市民参加を制度化し、多様な参加の機会を提供してきたプロセスを明らかにしました。特に、計画策定段階だけでなく、事業の実施や運営段階においても市民との協働を重視する姿勢への変化が指摘されており、継続的な関わりを通じた「エリアマネジメント」への展開を視野に入れている点が特徴的です。
また、都市計画ゲーム「つむぐ、ビジョン、マッチ」を用いた市民ワークショップのプロセスを分析した研究(論文53)は、ゲームという手法が未来のビジョンを具体的に想像し、それを地区の空間的変化と結びつける上で有効であることを示しました。参加者は、未来の活動シーンを描いたカードを選ぶことで、抽象的な議論に陥ることなく、自分たちの望む暮らしのイメージを共有し、それを実現するための空間計画へと繋げることができました。これらの研究は、現代的な市民参加が、単なる合意形成の手段ではなく、市民の創造性を引き出し、主体的なまちづくりへの関与を促すためのプラットフォームとして機能し始めていることを示しています。
地域活性化と新たな関係性の構築
人口減少社会における地域活性化は、従来の行政主導型モデルから、多様な担い手が連携する新たなモデルへと移行しています。
関係人口との協働: 岐阜県飛騨市を事例とした研究では、地域外から継続的に地域と関わる「関係人口」との協働に対する住民意識が分析されています(論文13, 28)。分析の結果、住民の意識は活動分野によって異なり、「新産業の展開」や「観光イベント」では協働に肯定的である一方、「伝統的な祭り」など地縁性の強い活動では慎重な姿勢が見られました。これは、関係人口との連携を進める上で、活動の特性に応じた丁寧なアプローチが必要であることを示唆しています。
移住者の地域適応: 同じく飛騨市を対象に、より良い生活の質を求めて移住する「ライフスタイル移住者」の地域コミュニティへの適応プロセスを質的に分析した研究があります(論文36)。この研究は、移住者が地域活動への参加や住民との交流を通じて「地域との繋がりや自己有用感」を得る一方で、「精神的孤独」や「住民との関係性」における困難に直面する実態を明らかにしました。移住者の定着には、移住者自身の努力だけでなく、地域側の受容意識の醸成が重要であることを示しています。
地域資源の活用: 東京都23区で開催されるマーケットの類型化と運営実態を分析した研究(論文10)や、Jリーグクラブが地域課題の解決にどのように貢献しているかを分析した研究(論文25)は、身近な地域資源を活用した活性化のパターンを示しています。マーケットは「地域コミュニティの形成」を目的とするものが多く、Jリーグクラブは「医療・健康・教育」分野での協業が多いなど、それぞれの資源の特性に応じた貢献の形が見られます。
包摂的な都市を目指す福祉と生活支援
すべての市民が安心して暮らせる包摂的な(インクルーシブな)都市の実現は、都市計画が果たすべき重要な社会的役割です。
障害者、高齢者、子どもなど多様な人々が交わる「ごちゃまぜ」の共生型福祉拠点の運営実態を分析した研究(論文39)は、その理念の実現に向けた課題を浮き彫りにしました。利用者の多様化が進む中で、ケアの必要な利用者が増え、スタッフの負担が増大し、地域住民との交流に十分な時間を割けないというジレンマが指摘されています。これは、福祉事業の収益構造と理念との間の緊張関係を示しており、持続可能な運営モデルの構築が課題となります。
また、木造住宅密集地域における買物支援策を評価した研究(論文37)では、住民が「空き地の活用」や「商店街の再生」といった身近な場所での買物の場を望んでいることが明らかになりました。さらに、自動運転配送ロボットのような新たな技術に対しても導入意向が高いことが示され、地域の物理的特性(狭隘道路など)と住民ニーズ(近接性)に応じたきめ細やかな支援策の重要性が示唆されています。
よりマクロな視点からは、自治体の属性と希望出生率の関係を分析した研究(論文26)があります。この研究は、児童福祉費の割合が高い自治体や、域内での就業者の割合が高い自治体ほど希望出生率が高くなる傾向を明らかにし、子育て支援策や職住近接の都市構造が、人々の将来の家族形成に関する希望に影響を与える可能性を示しています。
エリアマネジメントと官民連携
持続可能な都市経営を実現するため、エリアマネジメントや官民連携(PPP)といった手法への関心が高まっています。
シンガポールのBID(事業改善地区)制度の成功・失敗要因を分析した研究(論文11)は、効果的なエリアマネジメントの条件について重要な示唆を与えています。成功している地区では、不動産所有者間の利害調整が機能し、行政との強力なパートナーシップが構築されているのに対し、解散した地区では財源確保の困難さや活動成果の不明確さが課題であったことが指摘されています。
一方、日本の地方中小都市におけるPPP事業の方式選択理由を分析した研究(論文38)では、多くの自治体が財政負担の軽減や民間ノウハウの活用を目的として多様なPPP手法を選択している実態が明らかになりました。PFI方式だけでなく、定期借地権方式や公設民営方式など、事業の特性や地域の課題に応じて柔軟なスキームが組まれており、画一的ではないPPPの展開が見られます。
これらの実践的な研究動向を理解する一方で、その背景にある、より根源的な都市や建築をめぐる思想や理論的潮流を探ることも不可欠です。次章では、研究の新たな視座に焦点を当て、その知的フロンティアを展望します。
5. 都市・建築研究の新たな視座
本章では、従来の都市計画・建築研究の枠組みを拡張し、新たな問いを投げかける理論的・学際的な研究動向を分析します。ポスト人間中心主義、文化研究、歴史分析といった視座は、一見すると実務から遠いように思えるかもしれません。しかし、これらのアプローチは、複雑化する現代の都市問題をより根源的なレベルで理解し、これまでにない斬新な解決策を生み出すための知的基盤を提供する可能性を秘めています。その戦略的重要性を探ります。
ポスト人間中心主義と物質性への着目
人間を中心に世界を捉える従来の思想から脱却し、モノや環境といった非人間的存在の役割を再評価する「ポスト人間中心主義的マテリアリズム(PAM)」が、建築・都市研究の分野で注目を集めています。
この潮流を包括的にレビューした理論研究(論文3)は、その核心的な議論を整理しています。この潮流は、主に以下に挙げる複数の理論的系譜から影響を受けており、それらを包括する視座として理解されます。
- アクターネットワーク理論(ANT): 人とモノを対等な「アクター」とみなし、それらの相互連関のネットワークとして社会事象を記述するアプローチ。建築を設計する建築家だけでなく、図面、模型、法規制、建材といったモノも等しくアクターとして捉えます。
- 新物質主義(NM): 物質そのものに内在する能動性や自己組織化する力に着目する思想。物質は人間に操作されるだけの受動的な存在ではなく、空間や身体のあり方に積極的に働きかける力を持つと捉えます。
- ソシオマテリアリティ(SM): 社会的なもの(ソシオ)と物質的なもの(マテリアリティ)は分離不可能で、相互に構成しあう「絡み合い」として捉える視点。組織論などで、テクノロジーが人々の働き方やコミュニケーションをどのように変容させるかを分析する際に用いられます。
これらの理論的視座に共通するのは、建築や都市を「静的なオブジェクト(客体)」としてではなく、多様なアクター(人間・非人間)の相互作用によって絶えず生成・変容していく「動的なプロジェクト(過程)」として捉え直す点です。この視点は、スクラップ&ビルドを前提とした20世紀的な都市観から脱却し、既存の建築物や都市環境が持つ潜在的な力を再発見するための新たな理論的基盤を提供します。
都市文化と空間体験の分析
都市を物理的な空間としてだけでなく、文化が生まれ、人々が意味を体験する場として捉える学際的なアプローチも活発化しています。
1970年代から80年代にかけて流行した音楽ジャンル「シティ・ポップ」の歌詞を自然言語処理で分析した研究(論文6)は、その時代の都市イメージの変遷を鮮やかに描き出しました。初期には「街」が「孤独」や「アスファルト」といった言葉と結びついていたのに対し、時代が進むにつれて「海」や「車」、「リゾート」といった享楽的なイメージへと変化していく様相を定量的に示しています。これは、ポピュラーカルチャーが都市の表象としていかに機能してきたかを解明する試みです。
また、認知科学的なアプローチを取り入れた研究として、街歩きツアーにおける写真撮影が参加者の記憶に与える影響を実験的に検証したものがあります(論文18)。その結果、写真撮影行為そのものは、景観に関する視覚的な記憶(シーン記憶)に有意な影響を与えなかったものの、ガイドの説明内容に関する聴覚的な記憶(エピソード記憶)を低下させる傾向があることが明らかになりました。一方で、参加者が自発的に撮影した写真の枚数が多いほど、視覚的な記憶の正答率が高まるという興味深い関係も見出されました。これらの研究は、人文科学や認知科学との融合が、人々の都市に対する認識や体験といった主観的な側面を解明し、より人間中心の空間デザインに貢献する可能性を示しています。
歴史的・文化的資産の価値評価
歴史的・文化的資産の価値を、従来の美学的・歴史的評価だけでなく、経済的・社会的な側面から多角的に捉え直す研究も登場しています。
英国の会計基準「FRS30」を基に、文化財の会計的価値をどのように認識し、財務諸表に計上すべきかを論じた研究(論文2)は、文化財を単なるコストのかかる維持対象としてではなく、社会に貢献する「資産」として捉える新たな枠組みを提示しました。これは、従来、文化財の会計処理に一貫性がなく、財務諸表に計上されない資産が多数存在することで、その社会的価値が適切に認識されていなかった問題意識に対応するものです。文化財の価値を会計情報として「見える化」することで、その保全と活用に向けた社会的な認識を高め、より効果的な資金調達や政策決定に繋がる可能性が論じられています。
また、歴史学的なアプローチとして、明治初期の日本人使節団が残した記録を一次資料として、19世紀後半のテヘラン(イラン)における都市改造を再評価した研究があります(論文5)。当時のヨーロッパ列強とは異なる、同じく近代化を目指す途上国であった日本の視点から都市の姿を読み解くことで、西洋的な都市計画モデルがローカルな文脈でどのように受容・変容されたのかを複眼的に描き出しています。これは、西洋中心の近代都市計画史観を相対化し、非西洋諸国が近代化をどのように受容・変容させたかを多角的に理解する上で貴重な視点を提供します。
これらの研究は、経済学や歴史学といった他分野の視点や手法を積極的に取り入れることで、都市遺産の価値認識を拡張し、その保存と活用のあり方についてより豊かな議論を可能にすることを示しています。理論、文化、歴史といった多様な視座が交差する現代の研究動向を踏まえ、最終章では、これらの潮流を統合的に総括し、今後の展望を描きます。
6. 結論:都市計画・建築研究の統合的展望
この記事では、近年の都市計画・建築分野における研究動向を、「都市構造」「交通・人流」「環境・防災」「コミュニティ・ガバナンス」「新たな視座」という5つのテーマから概観しました。これらの分析を通じて、現代の研究におけるいくつかの重要な潮流が浮かび上がってきます。
第一に、「データ駆動型解析の主流化と、それによって浮き彫りになる質的側面の重要性」です。交通系ICカードやGPSデータを用いた人流解析は、市民の行動パターンをかつてない解像度で可視化し、LRT導入の効果検証や再開発の影響評価に客観的な根拠を提供しています。しかし同時に、データは「なぜ」人々がそのように行動するのかまでは教えてくれません。デマンド交通の研究(論文43)が示したように、住民が「安心感」という数値化しにくい価値を重視していることや、街歩きツアーの研究(論文18)が写真撮影と記憶の関係を論じているように、ビッグデータ解析が深化するほど、人々の主観的な認識や体験といった質的な側面を理解する必要性が逆説的に高まっています。
第二に、「分野横断による社会・環境課題への統合的対応」の動きです。気候変動や自然災害といった課題は、もはや防災や環境工学だけの問題ではありません。洪水リスクと人口動態の乖離(論文50)、グリーンインフラの多面的価値評価(論文16, 29, 30, 31, 32)、建築物の木造化による脱炭素化(論文9)など、土地利用計画、経済、景観、建築といった多様な分野が連携し、都市のレジリエンスという共通目標に向けて統合的にアプローチする研究が増えています。同様に、福祉、子育て、地域活性化といった社会的課題に対しても、ハードの整備とソフトの運営を一体で捉える視点が不可欠となっています。
第三に、「実践と理論の往還による知の深化」です。立地適正化計画やエリアマネジメントといった実務的な政策・制度を対象とした評価研究は、その効果と意図せざる課題を明らかにし、制度改善へのフィードバックを提供しています。その一方で、ポスト人間中心主義(論文3)のような理論的研究は、建築や都市を「動的なプロセス」として捉え直す新たな知的フレームワークを提示し、実践の現場に潜む固定観念を問い直すきっかけを与えています。実践から課題を抽出し、理論が新たな視座を提供し、その視座を以て再び実践を検証するという、両者の健全な往還関係が、研究分野全体の深化を促しています。
これらの潮流の中で、共通する課題も見えてきます。ビッグデータ活用の倫理的な側面、専門家によるトップダウンの計画と市民参加によるボトムアップのプロセスの最適なバランス、短期的なプロジェクト評価と持続可能な都市の長期ビジョンをいかに接続するかといった問いは、多くの研究に内在する根源的な課題です。
今後の都市計画・建築研究は、これらの潮流と課題を踏まえ、より一層の分野横断と理論・実践の往還を加速させていく必要があります。複雑化する社会・環境課題に対して、データに基づいた客観的分析能力と、人々の暮らしや文化に対する深い洞察力を兼ね備え、レジリエントで、包摂的かつ持続可能な都市の実現に貢献すること。それこそが、今、アカデミアに課せられた重要な役割であると言えるでしょう。
注意
以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。
学会参加について
学会で発表される全ての論文の内容を理解できるはずもありません。しかし、論文発表の際、冒頭で研究分野の位置付け・概要・既存研究などが集約されて紹介されます。そこを聞くだけでも、研究の積み重ねの体系が見えてきます。また、質疑応答を聞くと、その分野における広さ深さ他分野との関連などが見えてきます。1件の論文発表と質疑応答で20分ほどに限られますが、その研究は1年〜数年に渡り調査・分析・検証を重ね査読(第三者の検証)されてきた物なので、その数年分の知見を20分で受け取る濃厚な時間です。また、懇親会ではできるだけ多くの先生方と交流し自分が無知である中で短く質問すると、多様な知見を得ることができます。ということで、恐れずに学会に出向きお邪魔にならない程度に学んでいくことはとても有意義だと思えます。そうした「学びたい」「貢献したい」意欲を持つ方を学会は歓迎してくれるはずです。
遅ればせながら交通も市民参画はじめています
11月30日のフォーラム、ぜひご参加ください。