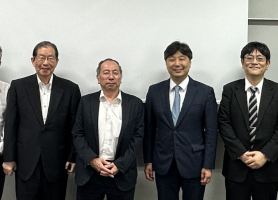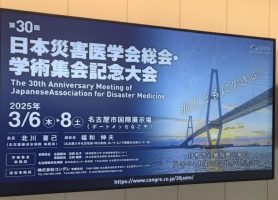目次
鉄道を活かして、より多くの命をより効率的に救いたい
従来の柔軟・高速な救急搬送に加え、災害時に大量に発生する傷病者の広域搬送に鉄道を活用する
大規模災害時、普段からケアが必要な方に加え、傷病者が多く発生します。被災地や周辺での医療活動は重症者のケアも重なり、大変な負担となります。ここで、被災地から傷病者を非被災地に広域搬出できると、被災地や周辺での医療活動は搬送できない重症者に集中することができます。現状の航空や自動車による搬送では少人数を柔軟かつ高速に搬送することができますが、大量の傷病者を運ぶ手立てがありませんでした。ここに大量・高速・定時の輸送特性を持つ鉄道を活用し、被災地から大量の傷病者を計画的に搬出する活用を考えています。
鉄道も被災するが、救えるのか?
鉄道施設が地震や津波で破壊されたセンセーショナルな風景が報道されます。ただ、これは一部に限られ、翌日からは激甚被災地の近くまで鉄道は運行を再開しています。Rail DiMeCでは、鉄道が運行できる最前線で条件を満たす駅を「医療中継拠点」とし、ここから鉄道で大量搬送を行うことを想定しています。
全国から被災地へ向けて(救援人材・物資の搬送)
- 現状と課題
- 全国各地から各自が所有する自動車でで人員と医療資機材を送り込み
- 長距離運転・長時間移動により、災害医療従事者の負担が大きく事故リスクも生じる
- 災地における活動時間に加え、現地との往復に要する時間が長く、派遣側の病院にも負担がかかる
- 鉄道を用いた解決案
- 緊急車両、医薬品、医療資機材は、鉄道(貨物)を利用して大量・長距離に輸送。医療スタッフは、新幹線や飛行機を利用して、短時間・軽負担で移動
- 災害医療従事者の移動負担軽減により、被災地内における医療活動の一層の充実化
- 派遣総日数(職員不在期間)の短縮化により、派遣側病院の通常診療の負担を軽減
被災地から近隣以遠への被災者の搬送
- 現状と課題
- 個々の救急車で救出地点から非被災地まで長距離搬送
- 救急車1台あたりで搬送できる患者数が少ない
- 救急車ごとに運転要員と医療要員が必要となる
- 個々の救急車が長距離移動する必要があり、渋滞の発生、渋滞による搬送遅延や予測困難の要因となる
- 鉄道を用いた解決案
- 被災地隣接の駅に医療拠点を設けて、救出地点から医療拠点駅までを救急車で、医療拠点駅から非被災地へは鉄道で搬送する。途中各駅から受け入れ病院へ患者を引き渡す。
- 鉄道で患者を集約的に大量輸送する。
- トリアージ(要医療度による振り分け)にて車両ごとに必要な医療を区分けし、搬送中にも少ない医療人員で複数の患者を集中的にケアする。
- 自動車(救急車)の移動を被災地近隣に留めることにより、道路使用量を抑え、鉄道移動により渋滞のないスムースな搬送を実現。
被災地に近い駅などに医療中継基地を設置
被災者の搬送が集中する鉄道駅など拠点となる場所に「中継基地」を設置し、自動車搬送と鉄道搬送を結節し、限られた資源で効果を最大化する医療オペレーションを実現します。