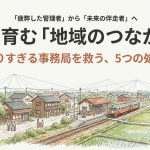目次
「都市を殺す常識」を打ち破れ!
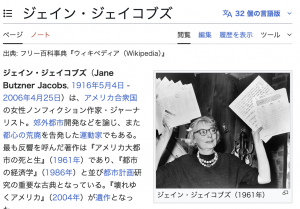 私たちが暮らす街は、本当に人々の生活を豊かにし、安全を守っているでしょうか。今から60年以上前、アメリカのジャーナリスト、ジェイン・ジェイコブスの著書『アメリカ大都市の死と生』(1961年)は、都市計画の専門家の常識を根底から覆しました。
私たちが暮らす街は、本当に人々の生活を豊かにし、安全を守っているでしょうか。今から60年以上前、アメリカのジャーナリスト、ジェイン・ジェイコブスの著書『アメリカ大都市の死と生』(1961年)は、都市計画の専門家の常識を根底から覆しました。
彼女の思想は、
「都市の活力と安全は、専門家による大規模な計画ではなく、日常的な地域住民の交流と、多様性に富んだ環境から自然発生的に生まれる」
という、シンプルかつ革新的なものでした。都市を「活気に満ちた有機的な生命」として捉えたジェイコブズは、当時の主流であったトップダウン型の計画、都市計画思想を痛烈に批判し、専門家や官僚が上から行う都市設計の権威を失墜させ、モダニズム都市計画の終焉を決定づけました。
動画概要
ジェイコブスが戦った「都市を殺す常識」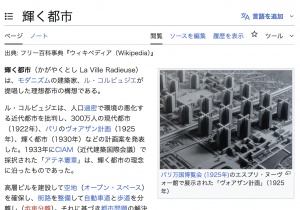
ジェイコブスは、正統派都市計画理論の「ゾーニング(用途地域制)や住宅ローン制度、大規模な再開発を優先するトップダウン的なアプローチが、連邦および州政府の法律やガイドラインに組み込まれ、「都市の活気に満ちた有機的な生命」を破壊していると主張しました ¹。その目的は用途が分離され、自動車に依存する非人間的な都市パターンが法的に推進されてきたことに、異議を唱えることでした。
- ル・コルビュジエの「輝く都市」:都市の機能を完全に分離し、高層ビルと高速道路を組み合わせた合理主義的な設計に対し、ジェイコブスはそれを「すばらしい機械式の玩具」だと皮肉り、用途を分離し、巨大なブロックに人々を隔離する計画が、都市の活気を殺していると主張しました¹。
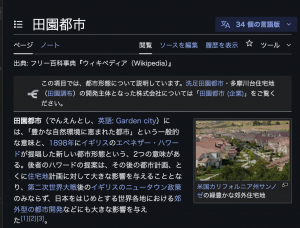
- エベネザー・ハワードの「田園都市」:エベネザー・ハワードの「田園都市運動」は、大都市の弊害を避け、自然と共存する自給自足型の小規模な町への移住を促す発想です。ジェイコブズは、この発想を、都市が持つ「文化的な創造性」や「経済的な爆発力」を無視し、大都市の機能を逃避させる「父権主義的な行為」だと断じました。田園都市的は日本の「ニュータウン」や「閑静な住宅街」として信奉されてきましたが、結果として「職住近接」や「多様な交流」を奪い、昼間に人が消え、夜には店舗が閉まる街を生み出しています。
活気を生む「人間的なスケール」と「多様性」
ジェイコブズが提唱した「人間らしい都市」の条件は、私たちが本来持つ「コミュニティの力」を取り戻すための設計図です。
「歩道のバレエ」と「ゆるやかな信頼」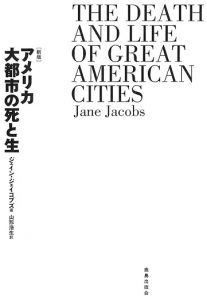
ジェイコブズが最も重視したのは、日常の街路で起こる「住民間の自発的な交流」です。彼女はこれを「歩道のバレエ」(Sidewalk Ballet)と呼びました。この交流は、多様な人々が多様な目的で街路を利用する中で、無意識的に繰り広げられる複雑な活動です。
- 交流の性質: 挨拶、目が合う、店の主人との短い会話、子供の遊びを見守ることなど、非公式で無目的なやり取り。
- 信頼の性質: 深いプライバシー侵害を伴う親密な関係ではなく、必要に応じて助け合える程度の「ゆるやかな信頼」(Loose Trust)の積み重ね。
この「歩道のバレエ」が街路に面した建物や活動から「街路の目(Eyes on the Street)」を生み、都市の安全が地域住民の無意識の相互監視で保たれると主張しました。
- 治安の維持: 常に誰かの目が街路に向けられ、防犯カメラより強力な「自発的な管理」が機能する。
- 安心感の醸成: 家の外に出れば誰かと目が合い、必要な情報や助けを得られる「健全な緩衝地帯」が形成される。
多様性と人間的なスケール:歩行者中心の適切な尺度
「人間的なスケール」(Human Scale)とは、建物の大きさではなく、人間の身体的感覚と社会的行動に適合した「適切な尺度」を意味します。活気に満ちた、人間らしいスケールの都市環境を生み出すための秘訣として、彼女は以下の「多様性の四条件」を提案しました。
- 用途の混合: 住居、店舗、オフィスなど、複数の機能が一つの地域に混ざり合い、異なる人々が異なる時間帯に利用することで、「街路の目」を絶えず保つ。
- 小さな街区:街路や交差点が多く、歩く中で角を曲がる機会が頻繁。角を曲がるたびに発見があり、回遊性とささやかな交流を促進され、信頼が形成される。建物や対向側が近く、自然な監視(Eyes on the Street)が機能しやすい狭い街路。
- 年数を経た建物の混合:古い建物と新しい建物が混在すること。古い建物は家賃が安いため、多様な所得層や中小企業が共存でき、経済的な多様性が保たれる。
- 高い人口密度:目的を共有し、交流するために十分な人々が密集し都市の活力を生むための「十分な密度」を保つ。
こうして見てると、自動車が悪いのではなく、広い道路や歩いて暮らせない自動車通行を優先した街づくりが街の活力を破壊してしまい、シャッター街やコミュニティの希薄化を生んでしまったと思えます。
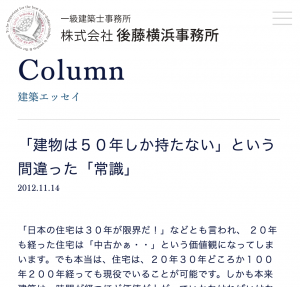 日本の都市再生
日本の都市再生
彼女はまた、1950年代のアメリカ諸都市で蔓延していた「スクラップ・アンド・ビルド型再開発」を、既存の社会構造や経済生態系を破壊し、都市衰退の主要な要因であるとして猛烈に反対しました。戦後の日本は、このアメリカ型の「自動車中心主義」と「用途分離型」の設計思想を採用してきました。都市計画法における硬直的な用途地域制は、ジェイコブスが重視した「用途の混合」を構造的に妨げました。
その結果、日本では長年にわたり、短期間での建て替えサイクル、「スクラップ&ビルド」が続いています。日本の硬直的な用途地域制と短期間での建替え文化は、この路地裏の文化を破壊し、街の活気を奪いました。国土交通省によれば、木造住宅の平均寿命は概ね64年程度であり、短期的な経済回転率(フロー)を優先する構造が根強く残っています²。
日本も変革を目指している
 日本の都市政策は今、人口減少と高齢化に対応するため、ジェイコブズの思想に近づこうとしています。
日本の都市政策は今、人口減少と高齢化に対応するため、ジェイコブズの思想に近づこうとしています。
- 立地適正化計画(都市機能と居住の集約を目指す)
- ウォーカブルなまちづくり戦略(「居心地がよく歩きたくなる空間」を目指す)³
これらの政策は、ジェイコブズが提唱した人間中心の都市の実現に向けた試みです。例えば、福岡市の「天神ビッグバン」⁴では、車道の一部を削減し、広場やオープンスペースを拡大することで、歩行者の回遊性を高める試みが進められ、「自動車よりも歩行者に焦点を当てた、比較的狭い街路」というジェイコブズのアイデアの実践にほかなりません。
しかし、これらの計画は私有地への強い強制力を伴わず「緩やかな誘導」にとどまっているため、構造的な転換は難航しています⁵。この課題を乗り越えるには、行政の誘導だけでなく、地域住民が自ら「街の活気と安全は自分たちが作る」という意識を持ち参画する必要があります。
「お天道様が見ている」「路地の触れ合い」を思い出そう
米国では各地にLRTが建設され、シアトルやポートランドなどでジェイコブズ的な都市再生が劇的に進んでいますが、日本ではなかなか前には進んでいません。実は、ジェイコブズが目指した都市の姿は、古来より培ってきた日本の「町民文化」に近いものです。これらは日本人の心に根付いている風土ですので、住民がその価値を思い出すだけで良いのです。
- 「お天道様が見ている」という倫理観:ジェイコブズが提唱した「街路の目」は、まさしく日本の伝統的な相互監視・自己規制の倫理観である「お天道様が見ている」という倫理観に重なります。
- 路地裏の交流文化:戦前の日本には、ジェイコブズの「用途の混合」「小さな街区」「古い建物の混合」を自然に体現した、「路地裏の交流文化」が色濃く残っていました。
- 事例: 京都の京町家や金沢の古い街並みでは、住居の軒先で商売が営まれ、子どもたちが路地で遊び、近隣住民が井戸端で情報を交換する。これは「歩道のバレエ」そのものです。
都市を理解してから交通を考える
最後にジェイコブズの痛烈なひと言を引用します。
「自動車はしばしば、都市の弊害や都市計画の失敗と無益さの原因として都合よくレッテルを貼られる。しかし、自動車の破壊的な影響は、原因というよりむしろ、都市建設における私たちの無能さの兆候である。自動車の単純なニーズは、都市の複雑なニーズよりも理解しやすく、満たされやすい。そして、ますます多くの都市計画者や設計者は、交通問題を解決できれば、都市の主要問題を解決できると考えるようになっている。都市は、自動車交通よりもはるかに複雑な経済的・社会的問題を抱えている。都市自体がどのように機能し、街路に他に何をする必要があるかを理解しなければ、交通に関して何を試みるべきかを知ることはできないだろう。それは不可能だ。」
– ジェーン・ジェイコブズ著『アメリカ大都市の死と生』 、1961年
交通を語るなら、もっと都市を理解しなければなりませんね。64年前からのお叱りでした。ということで、まだまだ続きます。。。。。
出典 (2025年10月6日 閲覧)
- 1 ジェイコブスの著作がモダニズム都市計画を批判し、複雑系の科学を先取りする代替研究方法を示唆したこと。
名著探訪 The Death and Life of Great American Cities (日本都市計画学会) - 2 住宅の長寿命化に関するレポートより、木造住宅の平均寿命(64年)と「200年住宅」の概念。
「建物は50年しか持たない」という間違った「常識」 - 3 ウォーカブルなまちづくりの先進事例
鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン検討資料 - 4 ウォーカブルシティの概要と国内外の事例。
ウォーカブルシティとは?もたらす効果や国内外の事例を解説
なぜ車道をつぶして歩道にするの?→「儲かる」からです! 全国で相次ぐ再整備のワケ 「高速道路廃止」も - 5 立地適正化計画の国のKPI(居住誘導、都市機能誘導)の低下傾向、私権規制の回避(居住調整地域)、PDCAサイクルの未実施状況。
【公共コンサルと政策の視点】高い実効性を伴った立地適正化計画の運用を実践するための重要課題(2/2)(長谷川一樹)(2024年9月18日)
音声概要
- 投稿タグ
- #academic, #Citizen, #Urban design, #US, #Video, #Voice, #Wikipedia, #思想