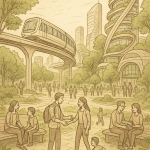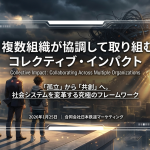自動車は移動の自由、経済発展、雇用、税収、など様々な社会貢献をしています。また、ロードムービーなど映画のジャンルも作り、ドライブイン、ドライブスルー、郊外型ショッピングセンターなど様々なビジネスも生み出しました。一方で、公害や中心街の衰退など街も変えるほどの変化を起こしました。ここでは功罪ある自動車の社会的影響について淡々と見ていきたく思います。
音声概要をお聞きいただけます
 Notebook LM に英語版 Wikipedia 記事を学習させ生成した音声概要をこちらよりお聞きいただけます。
Notebook LM に英語版 Wikipedia 記事を学習させ生成した音声概要をこちらよりお聞きいただけます。
Wikipedoa の記事
 Wikipedia には、記事について執筆者同士が対話する Talk という場所があるのですが、英語版記事の Talk を見ると、20年以上に渡りさまざまな議論が積み重ねられてきたことがわかります。「当初は自動車文化」といった軽い内容だったようですが、百科事典ならば社会的側面の功罪も挙げるべきだとか、もっと客観的にとか議論を重ね、記事の名前も変更してと大変な労力がかかっていることがわかります。
Wikipedia には、記事について執筆者同士が対話する Talk という場所があるのですが、英語版記事の Talk を見ると、20年以上に渡りさまざまな議論が積み重ねられてきたことがわかります。「当初は自動車文化」といった軽い内容だったようですが、百科事典ならば社会的側面の功罪も挙げるべきだとか、もっと客観的にとか議論を重ね、記事の名前も変更してと大変な労力がかかっていることがわかります。
そのため、記事の内容は膨大で、とても充実したものになっています。音声概要のおかげでざっくり把握はできますので、興味を持った部分を読み深めていくと良いでしょう。
自動車都市や自動車依存・自動車の外部性と重なる部分も多いので、ここれはそれ以外のところを取り上げましょう。
経済的なインパクト
1900年代初頭に自動車が急成長したのは自動車都市でも触れましたが、。フォードで働いていた労働者が1万4366人(1913年)が、13万2702人(1916年)に増加ですから、3年で10倍弱という凄まじい成長です。ネット企業と異なりラインで製造する「実業」ですから、とんでもない設備投資が伴ったことが伺えます。フォード式生産方式がいかに拡張性に優れていたかということがわかります。1tを超える大きな機械を大量生産するというのは、他の産業には無い特徴です。公共交通と比較したとき、この「製造量と改善の積み重ね」にいかに向き合うかというあたりは考えるべきところでしょう。
路面電車型郊外住宅地
この記事の郊外社会の到来で「路面電車郊外 (Streetcar suburb)」という言葉が見られます。郊外住宅地は鉄道路線、市内に直通すると路面電車となる欧州で言えば「トラムトレイン」の形態であるインターアーバンが1901年から急速に発展し、1930年頃から姿を消しました。路面電車型郊外も時期はほぼ重なっている模様です。どうも路面電車がそのまま郊外に伸びて郊外都市を形成していた模様なのです。郊外に碁盤の目状の街路を作り、電停近くにコンパクトな住宅や商店で設計された街並みを作るのはスマートグロースに通じる考え方です。日本のTODがインターアーバンから都市作りを学んだと言われていますが、この路面電車郊外がその大元なのかもしれません。路面電車型郊外住宅地は自動車都市に飲み込まれ、駐車場が無い小さな家並みは取り壊され、姿を消します。しかし、現在スマートグロースの最先端であるポートランドやオースティンに路面電車郊外があったのは、素地があったということなのでしょう。
自動車の保有コスト
個人または内部コストに書かれている自動車保有コストも興味深いです。米国では州によって年額2,024〜4,233ドル、カナダで約7300米ドルとさらに上がります。シンガポールはもっと高いのではと思えますが、日本では燃費・高速代を抜いて一台40万円くらいなのでカナダ以上でしょう。狭い日本では自動車はなかなかな贅沢品です。
消費者速度
これも初めて聞いた概念ですが、車での総移動距離を、車時間(車に関して費やしたすべての時間。運転やメンテ、購入費のために働く時間も含む)を割れば 距離➗時間 で速度になります。これがなんと7.6 km/hだそうで、小走り位の速さですね。あれ?ならば車無しで小走りすれば同じ生産性になるということでしょう。これは考えさせられる数字です。車を走らせて働くのではなく、実は車のために働かされているという現実に気付く面白い計算です。
印象のまとめ
普段、公共交通をなんとかしようとしていると、自動車にやられっぱなしなのでついつい敵視しがちですが、自動車がもたらした経済は圧倒的なもので、この恩恵は私たちも受けています。行き過ぎれば害が出るというところなので、どのように折り合いを付けていくのかが大事で、そのためには自動車って一体何なのかを改めてスタディするのは結構な気付きがありました。
自由を好む自動車が好きな人、運転できない人、能率・効率を求める人、いろいろです。東京では鉄道無しではなかなか暮らせませんし、地方では車無しでは暮らせません。日本全体では選択肢があるというのは、案外豊かなのかもしれません。また、路面電車郊外が日本に波及した後に姿を消して、日本では発展し、米国では再びスマートグロースで復活している。このような歴史の不思議な流れも感じられて面白いですね。
さて、これから公共交通をどうするかは、地域ごとに作戦は変わります。でも、全く自動車に歯がたたないという訳でもないということも確信が持てました。
- 投稿タグ
- #academic, #Car dependency, #TOD, #Urban design, #US, #Voice, #Wikipedia, #自動車